上場株式の売買注文を出す際、成行注文であっても、注文確認画面に「●●円~○○円」という目安の金額や概算約定金額が表示されていることにお気づきでしょうか。
これは、株価が1日の値動きが大きすぎないように、証券取引所がその日の株価の上限と下限を「制限値幅」として定めているためです。制限値幅とは、前営業日の終値や気配値を基準にした、その日の上下の値動きの範囲のことです。
「制限値幅」によって、日々の株価の動きは上限と下限が決まっている
制限値幅が設けられていることによって、上場株式は株価がその日の上限に達すると「ストップ高」となり、その日はそれ以上には上がりません。同じように、株価がその日の下限に達する「ストップ安」も、それ以下には下がりません。
「ストップ高」「ストップ安」とは、売買が成立しないまま買い注文や売り注文が「買い気配」「売り気配」として残った場合に、一定の配分ルールで注文を割り当てることです。
この上限・下限までの制限値幅は、証券取引所が株価水準に応じて、段階的に定めています。東京証券取引所の制限値幅は、前営業日の終値又は気配値を基準として、【表】のようになっています。
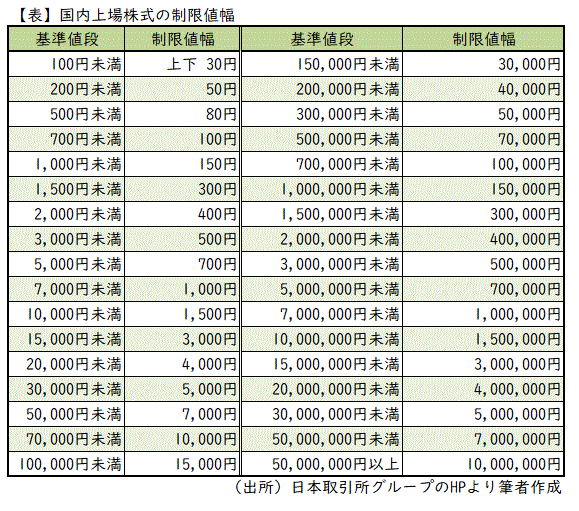
例えば、前営業日の終値が480円であれば制限値幅は80円なので、翌日の値動きは560円から400円までになります。最大限株価が上昇しても、その日は原則として560円までしか上がりません。この状態は「現在の株価は560円でストップ高」といわれます。それでもなお買い注文を集めると、「560円のストップ高買い気配」となります。
値下がりの場合も同様で、上の例では、その日は原則として400円のストップ安までしか下がりません。さらに売り注文が集まると「400円のストップ安売り気配」になります。
また、株価は日々上下しています。株価水準が変われば、【表】で適用される制限値幅の枠も変わります。
冒頭の例で、「560円のストップ高買い気配」で取引が終了したと仮定します。すると翌日の基準値は560円ですから、値幅制限は【表】で1段階上がった100円に変わります。すると翌日の株価は、660円から460円の幅で取引されることになります【図】。
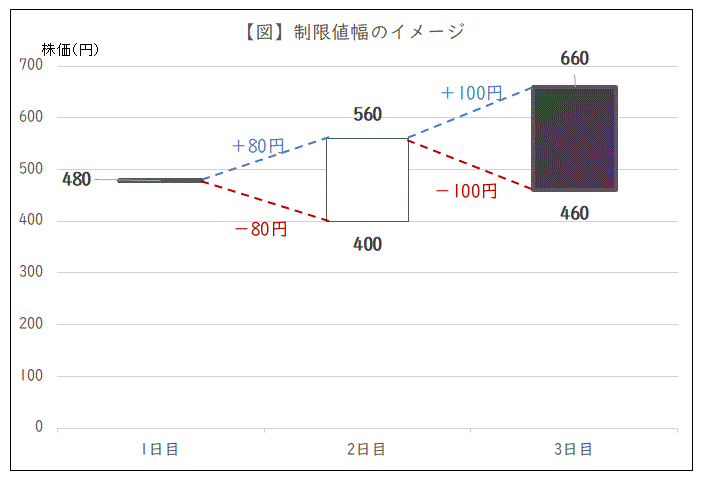
1日目の終値480円を基準にした2日目は値幅制限が80円でしたが、2日目の終値が560円になると制限値幅の【表】では1段階上がります。そのため、3日目の値幅は上下100円です。この日にストップ安になると、1日目の480円より低い株価になってしまいます。値動きの荒い相場の時には、ストップ高になった翌営業日に利食い売りが集中し、動き出した日より株価が下がってしまうことも珍しくありません。
成行で買い注文を出す場合の買付余力に注意
値幅制限は、成行注文で現物株を買う場合に気をつけなければなりません。買い注文を出すには、証券会社の総合口座に約定代金以上の預かり金やMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の残高が必要だからです。
指値注文であれば、「注文する株価×株数+手数料」の金額は明確ですが、成行注文の場合はそうはいきません。証券会社では、顧客の口座に「値幅制限の上限での株価×株数+手数料」の残高がなければ注文を出せないシステムになっています。
つまり、前営業日の終値が480円の銘柄の成行買い注文を出すには、値幅制限分を上乗せした「560円×株数+手数料」の残高が必要です。たとえ現在値がストップ安の400円だったとしても、成行買い注文では上限の560円が求められます。
臨時に制限値幅を変更する場合も
なお、証券取引所は、臨時に制限値幅を変更することがあります。例えば国内株式の場合では、2営業日連続で次のいずれかに該当した場合、その翌営業日から制限値幅を拡大することになっています。
(1) ストップ高またはストップ安となり、かつ、ストップ配分も行われずに売買高が0株だったとき
(2) 売買高が0株のまま大引けを迎え、取引終了時にストップ高またはストップ安で売買が成立し、かつ、ストップ高の場合は買気配を、ストップ安の場合は売気配を残したとき
また、ETF(上場投資信託)などやレバレッジ商品については、ストップ高またはストップ安の値段で取引終了となった場合、翌営業日から制限値幅が拡大されます。
これらの措置がなされた銘柄があった場合は、日本取引所グループのWEBサイト上のマーケットニュースに掲載されることになっています。
【参考】
日本取引所グループ 内国株の内国株の売買制度




 人気ランキング
人気ランキング












 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



