2025年7月28日、人工知能(AI)開発のオルツ社が第三者委員会による調査報告書を公開しました。粉飾の疑いがあり、売上高の過大計上は約119億円にのぼるという規模の大きい不正が明るみに出ました。広告代理店やパートナー会社を巻き込んだ「循環取引」が指摘されている一方、今後も同様の懸念が残ります。その背景にあるのは、2030年以降ともいわれるグロース市場の上場維持基準変更です。
グロース市場の上場維持基準変更とは?
まず前提として、オルツ社の粉飾事件はまだ動機が明らかになっていません。今後刑事事件に発展する可能性もあり、動機も含めて解明されていくことでしょう。その前提で話を進めていきます。
※オルツ社は7月30日、東京地裁に民事再生法の適用を申請したと発表しました。(7月30日18:00 追記)
グロース市場の上場維持変更とは、上場から5年が経過した企業に対し、時価総額100億円以上を求めるものです。2025年3月末時点でこの基準に達成していない企業は約420社にのぼり、グロース市場全体の68%を占めます。
この企業群に対して上場廃止を掲げることによって、他市場に移るか上場廃止が迫られます。筆者はスタートアップにも関係深い立場でこのニュースを見ましたが、「不祥事の防止」を目的としたこの荒療治が適用する前に、目に見える形で「起業家へのリスペクト」の風潮を作るべきではないかと感じました。
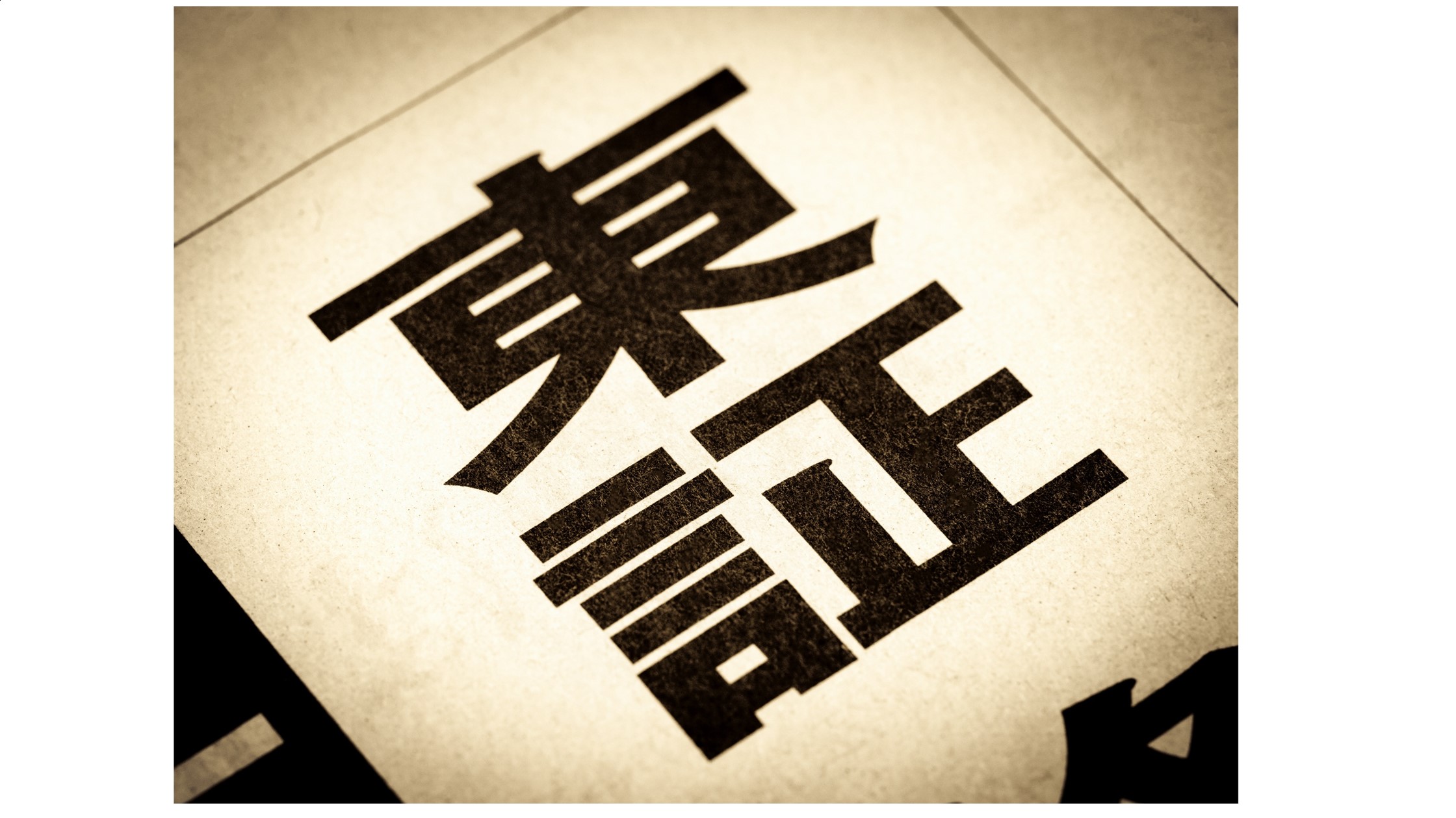
再起できない「スタートアップ起業家」
あくまで筆者の肌感ですが、2010年代中盤から日本でも隆盛したスタートアップ文化において、数々の新興企業が成長していきました。その一方で「スタートアップの90%以上は失敗する」という言葉の通り、多くの企業が退場していきました。
本来であれば、新市場の開拓を目指して挑戦した人材は日本にとって代えがたいものであり、社会的にも高い評価を受けるべきです。ただ実際は、一度失敗した人材が、とても厳しい評価を受けているという話を耳にします。
「あの人は一度失敗しているからね」という評価
たとえば企業としてデットファイナンスを実行していた場合、個人も連帯保証を求められます。数年前に「連帯保証の撤廃」が議論されましたが、その後に新規借り入れをする人が対象で、その時に既に借りていた人にはほとんど適用されなかった模様です。
その結果想定通りに市場が想定しないと、当然ながら資金繰りに苦しみます。その結果ビジネスを止めると、法人のみならず「個人としても破産」という扱いが待っています。数年にわたりクレジットカードは作成できなくなるほか、その時受注していた仕事も「破産」を期に契約が打ち切りになることもあります。
あくまで筆者の肌感ですが、驚くのはこれが「エクイティファイナンス」の経営者にも適用されているという話があります。想定通りの評価額でEXITが出来なかった場合、次の起業において資金が集まらないばかりか、再就職においても「あの人は一度失敗している」という評価がつくこともあるそうです。
企業の経営時には積極的にSNSを更新していた人のなかにも、退任してからまったく発信が無くなってしまう事例が目立ちます。なかには年に一度の誕生日のコメントに対しても音沙汰が無い場合もあります。言葉を選ばずにいえば「生きているのかすらわからない」という状態です。あれだけひとつの領域を詰めていた人間から、何も発信が無くなってしまうこと自体、社会としてはとても大きな損失です。
筆者は2023年に国産ロケット失敗を叩く社会の姿を見て、このハラキリ文化を強く感じ、「ロケット打ち上げ失敗とスタートアップとハラキリ文化」というタイトルで本メディアに寄稿しました。あれから2年、この危険な風潮は、何も変わっていないように感じます。
これが「成功の反対は失敗ではなく、挑戦しないことだ」という国なのでしょうか。背景には、これまでの日本文化で失敗者に対して責任を求めてきた、この「ハラキリ文化」が続いていると筆者は考えています。そして、これはシュリンクを避けられない今後の日本にとって大きなリスクです。

「起業家へのリスペクト」を根づかせたい
グロースの上場維持基準に、日本の市場を守る明確な目的があることは否定しません。ただ一方で基準変更により現職を追われた創業者や経営者が「あの人はグロースの変更で追い出された」となってしまっては、再挑戦の機会は確実に奪われます。
その結果、日本においてチャレンジの灯は今よりも更に小さくなり、海外からのサービスを享受するだけの「デジタル赤字国」になることが懸念されます。
国や地方自治体が法律を整備するという話ではないため、文化の醸成はとても難しいものです。ただ、これをおろそかにすると、何とか時価総額の適用を免れるために粉飾に手を出したり、起業の実態を膨らませて見せるようになるという流れが予測されます。それは、上場維持基準を変える市場自体が最も懸念する展開ではないのでしょうか。
繰り返しになりますが今回の粉飾事件と、グロース市場の維持基準変更に何かしらの関係があるかは、何も明らかになってはいません。ただ今回の事件が例外的にモラルの低い事例ではなく、多くの企業にとって発生することの無いように、警鐘を鳴らそうと思います。




 人気ランキング
人気ランキング




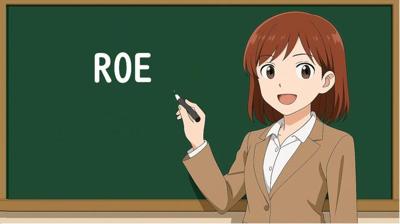







 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



