日経平均の最高値が連日更新されています。2025年8月13日の終値は前日556円50銭高の4万3274円67銭となり、過去最高値を更新しました。一方で株式市場が活況の際によく耳にするのは「我々の生活は決して良くなっていない」という街の声です。海外ファンドによる株価指数先物買いによる短期的な過熱感という指摘もあります。そこで専門家のひとりとして日経平均から敢えて目を離し、「ほかの統計」を見てみたいと思います。
株価のほかに「我々の生活を反映するもの」とは?
2024年に4万円の大台に乗った日経平均株価は、一時期停滞していたものの、当面の関税問題の落ち着きとアメリカの利下げがほぼ確定となったことで4万3000円台を突破しました。とはいえこの2年間我々の生活が際立って良くなった印象は少なく、かねてからの物価高も手伝い「日常生活との乖離」を強く感じます。世の中を示す数字は株式指標だけではありません。
まずはGDPを見ていきましょう。2024年度年次の名目GDPは3.7%、2025年1月-3月の四半期GDPは0.9%です。またGDPには前四半期の速報のほかに、「先行きの実質GDP」があります。8月13日の日経新聞によると、7-9月の先行き実質GDPは前年比年率で0.01%増と一時的な横ばいになる見通しですが、続く10~12月期は内需が下支えし、0.65%増になると報じられています。GDPからは、手堅く成長している印象を受けます。
GDP視点での生産の高まりを裏付けるのが企業経営者の見立てです。そこで最新の日銀短観をみていきましょう。7月1日に発表された6月期の短観では、企業の設備投資への意欲が順調に推移していることがわかります。特に2025年度の設備投資額の計画は前年度比6.7%増加する見通しで、前年度に人手不足などから先送りされた影響もあると分析されています。
この二つの統計を見てわかることは、海外投資家によって底上げされた株価ではあるものの、国内企業に対する期待感は確実に良くなっていることです。また関税に関しては今後の影響が懸念されるものの、自動車など一部の業種を除いて「どのくらいの影響になるのか推移を見守っている」という状況です。
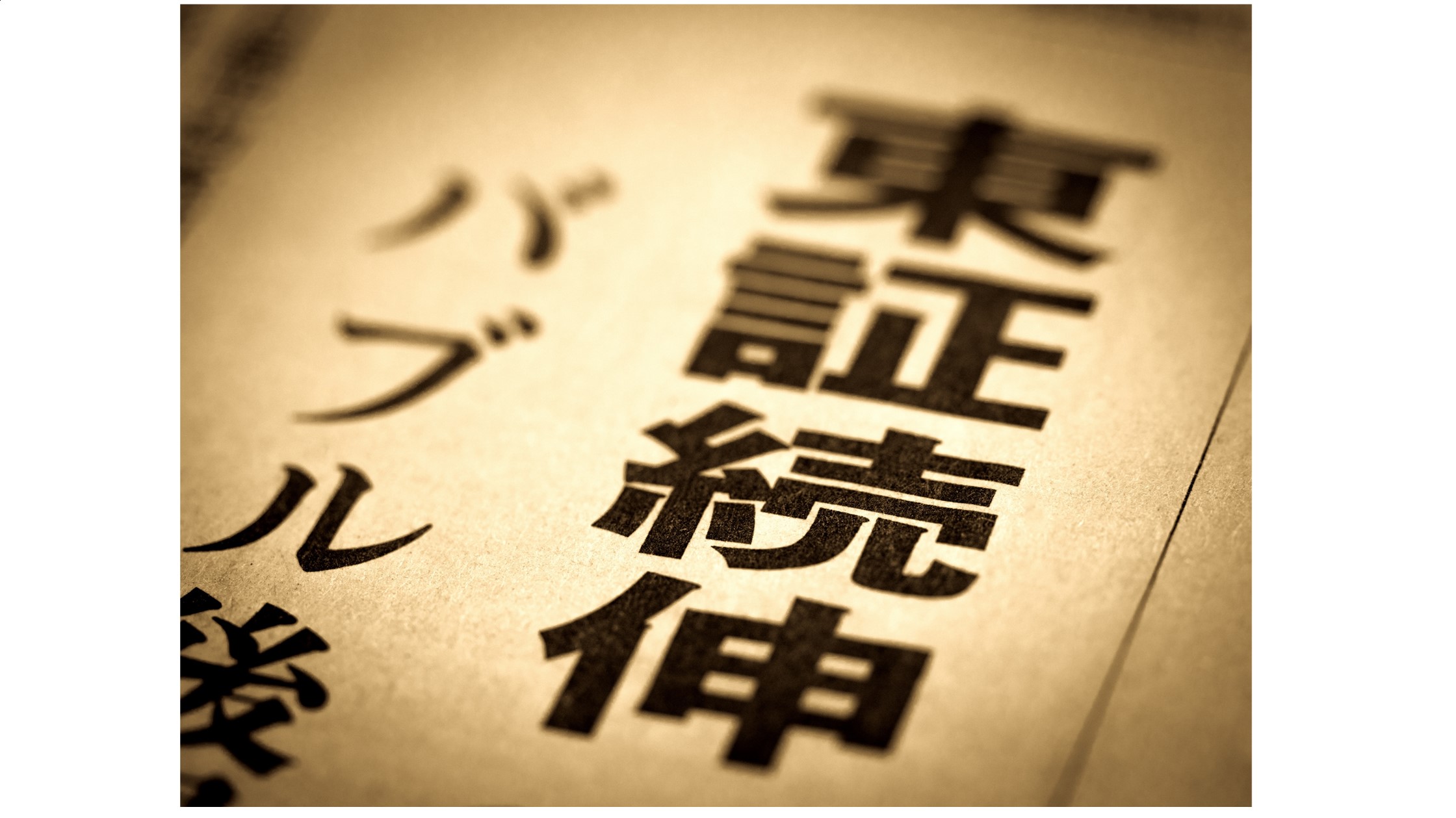
高水準の長期金利
次に実体経済に大きな影響を有するのが長期金利です。2025年7月15日のブルームバーグによると、2週間後に参議院選挙を控えた長期金利は一時1.595%に上昇しました。選挙結果により与党が過半数を割り込み、拡張的な財政政策に傾くと懸念されたことが背景です。
選挙の結果、実際に過半数割れが生じます。ただ短期間での連立政権樹立による財政政策の変更とはならず、8月14日の長期金利(新発10年物国債)は1.515%と、幾分落ち着いた印象です。今後秋の臨時国会に向けて政権の仕組みが固まってくると、長期金利にも次の展開に移行することが考えられます。
消費動向指数
消費動向指数は、2020年を基準として「世帯における平均支出額」を示す統計です。8月8日に発表された最新の2025年6月分では、2020年を100として名目104、物価変動を反映した実質GDPは91.4と発表されています。
注目すべきは前月比(季節調整値)です。こちらは名目2.3%、実質2.2%の減少です。季節調整値とは祝日や曜日などの影響を除いたもののため、ゴールデンウィークを考慮しない2025年5月の消費が活発であったことがわかります。かつ物価変動の影響は大きく、物価変動分まで消費が活発化してはいないことも統計全体から読み取れます。
消費者物価指数(CPI)
最後に登場するのは知名度の高い消費者物価指数です。アメリカと合わせCPIは株式相場にも大きな影響をもたらします。最新の2025年6月分では、2020年を100として111.7%、生鮮食品を除くと111.4%の上昇が発表されています。どちらも前年同月比3.3%の上昇であり、日銀が目標としている2%の物価上昇を超える上昇率と定義することができます。

「複数の統計」を見る習慣をつけたい
日経平均やTOPIXが過去最高値といっても、それが投資家の「熱量」に直結しているとは限りません。海外の投機筋による短期売買が影響し、また関税問題など「平時では想定できない背景」である場合があります。そのなかで各社の発表した決算報にもとづくファンダメンタルズや、過去を見てのテクニカル分析を妄信すると読み手を誤ることにも繋がります。
2025年の折り返しをすぎて3カ月。お盆を過ぎると心理的に日本は後半戦です。今年の前半はあまりにイレギュラーなことが多すぎて、蓄積疲労の個人投資家も多いでしょう。そんななかで到来した日本株の高騰です。落ち着いて判断するためにも、複数の統計を見て自身の「次の立ち位置」を定めていきましょう。




 人気ランキング
人気ランキング




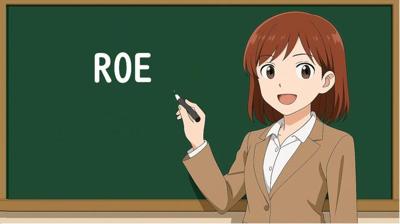







 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



