アメリカで「ブルーカラービリオネア」という言葉が注目されています。いわゆる建設業の現場職の方々において案件が途切れない状況が続き、比例して収入が著しく上昇している状況です。その理由はいま、社会を席巻している「AI」です。あらゆる仕事がAIによって代替されるなかでも建設関係は難しく、これまでのように人の手に頼ってという作業が不可欠です。
AIを入れるとコスパが悪くなる
まず断りをいれると、建設業全体の話ではありません。大手企業のゼネコン各社が展開する大規模な建築などでは、驚くような勢いでAIの導入が進んでいます。複数の現場において活躍するAIを整備できれば、それだけ建築コストが浮くためです。
ただ、鳶職や足場、基礎構築のように高い技術を必要とするものと、その技術が「職人の経験値に依るもの」であれば、なかなかAIが取って代わることはできません。AIを入れるコストパフォーマンスが合いません。
次に報酬が上がる仕組みについて解説します。「ビリオネア」は、そのような業界独特の背景によって建築業界の職人さんたちに仕事が集まり、待遇が良くなっていくことを指します。
需要に比べて供給側が不足すれば、対応単価が上昇していきます。これは筆者の推測ですが、「AIに負けない仕事を探そう」という世界全体の流れのなかで、建設業の人気が高くなっていく。そうすれば従来から活躍している方々は指導的立場となり、マネジメントを通して更に好待遇を得ることができます。
この三拍子によって、建築業界でビリオネアが生まれているという仮説が成立します。以前から比べると大きく変わっているとは思いますが、「俺の背中を見て学べ」の世界、マネジメント役はとても貴重な存在です。

日本においては実感がない?
日本においてはどうでしょうか。メディアなどを見ても、「ブルーカラービリオネア」が特集されている感触はさほどありません。女性首相や熊被害など、別のニュースに時間が割かれている印象です。
また筆者は月50本以上の資産運用の相談をしていますが、業界の近い方に話をしても「ビリオネア?聞いたことないですね」という反応がほとんどです。日本は建設会社やハウスメーカーなどの大手が案件を獲得することが多いため、現場の専門職は繁忙こそなれど、「ビリオネア」が生まれるような仕組みにはなっていないということでしょうか。
ほかにビリオネアが生まれる専門職は
数年前に週刊誌がよく特集していた「将来無くなりそうな仕事」の対極にある今回のテーマ。建設現場のほかにビリオネアが生まれそうな業界は何があるのでしょうか。
進まない自動運転
該当するのが自動運転です。モーターショーなどでは最新鋭の自動運転が注目されることも多いですが、一般道路を自動運転車が走りはじめる気配はありません。これだけ高齢者運転による事故が大きな問題となっているなかで進まないのは、万が一の場合の事故や設計ミスが許されないためです。
そう考えると過疎地のバスやタクシーなどは、代替案としてライドシェアが導入されそうなものですが、現実は異なります。導入実績も法律も限定的ななか、皆が首を長くして自動運転を待ち望んでいる状況、といえるでしょう。地方の狭い道を走るバスの運転手などは、今も昔も代わりの効かない存在であるといえます。

嗅覚・味覚のエキスパート
またきわめてクオリティの高いお酒やコーヒーの作り手なども、同じような発想で暫く重宝されそうです。「匂いを嗅ぐ」という行動も同じく、どれだけAIが発展しようが代替されるものではありません。
ビール好きの筆者は先般、サントリーのビール工場に足を運びました。そこで来館者に挨拶をしていたのは、ビールメーカーであるサントリーを司る「ブランドマイスター」の存在でした。ほかのビール会社はもちろん、様々な職種で会社が後押しをする「嗅覚と味覚のプロ」がいます。
2020年代前半から、フリーランスなどの働き方改革も手伝い、「これからは個人の時代だ」という流れが拡大していきました。その数年後に到来したAIの壁です。ただ注意したいのは、AIの適応力もまた、日進月歩で進んでいるということです。
建設業にはAIは適さないという記事を書いているうちに、世界のどこかでは建設業を大きく「ディスラプト(破壊)」するサービスが生まれ、きわめて短い時間で世界に広がっていく可能性もあります。ましてやそのなかで、AIに代替されない技術を時間をかけて身に着けるというのも、決して安全では無いと考えられるでしょう。人々のキャリアに、「充分な時間が与えられない世の中」です。
そうはいっても株式相場ではこれから先も、AIの波をかいくぐる人材、そして育成力を有する企業が重宝されていきます。投資家のみなさんがホールドしている会社には、AIに負けない人材がどれくらいいるでしょうか。




 人気ランキング
人気ランキング




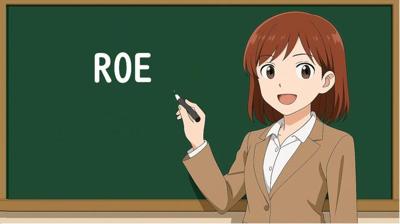







 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



