将来、突然の病気やケガで高額な医療費が必要になったとき、手元に十分な備えがなければ生活が一変してしまうかもしれません。
特に45歳を過ぎると医療費の負担は増える傾向があり「あのとき準備しておけばよかった…」と後悔する人も少なくありません。
しかし、毎月わずかな金額でも計画的に積み立てておくことで、将来の医療リスクにしっかり備えられます。さらに、公的制度や保険を上手に活用することで、家計の負担を最小限に抑えることも可能です。
本記事では、医療費積立の基礎知識から、年代・家族構成別の目安金額、実践的な積立方法までをわかりやすく解説します。将来に安心して備えるために、今からできる準備を始めましょう。
医療費積立とは?
医療費積立とは、将来の予期せぬ医療費に備え、計画的にお金を準備しておく家計管理の手法です。医療費のなかには病院やクリニックでの診察の他に、歯科治療や薬代も含まれます。
日本には公的医療制度がありますが、自己負担分や予防医療などは自己負担になることもあり、年間数万円の支出が発生することも。
加齢による健康リスクの増加、家族構成の変化などを踏まえ、事前に医療費を備えておくことで、急な出費にも慌てずに対応できます。

年代別・医療費はいくら必要になるか?
厚生労働省が発表している「令和4年度・国民医療費の概況」を参考に、国民1人あたりの年間医療費をみていきます。
0~14歳:約18.1万円
15~44歳:約14.3万円
45~64歳:約29.6万円
65歳以上:約77.6万円
ちなみに、18未満になる子供の医療費は各自治体で負担しているので、医療期間での窓口支払いは原則としてありません。
18~70歳までは医療負担が3割になりますので、一人当たりの年間の支払い額は18~44歳までで約4.8万円。45~64歳までだと約9.8万円になる計算です。
年齢が上がるにつれ医療費が増加するのは、身体機能の低下や生活習慣病、慢性疾患、定期的な検診の必要性などが影響しています。
家族構成による毎月の医療費積立額の目安
一人暮らしの20~44歳までの世帯では、年間の医療費支払いが月5,000円程度の医療費積立が適切です。健康診断、歯科検診、突発的な通院費用などに備えられます。45歳~50代になると、生活習慣病対策や定期検査への支払いを考慮し、毎月1万円程度の積立が推奨されます。
夫婦2人の場合、20~30代では妊娠・出産関連費用を考慮すると、月1万円の積立が望ましいでしょう。44~64歳になると、生活習慣病への備え、慢性疾患対策、クリニックや病院への定期通院を視野に入れ、月20,000円程度の積立が必要となります。
子育て世代の4人家族では、18歳未満における子供の医療費負担が原則発生しない観点から、夫婦2人暮らしでの医療費負担を参考に月15,000円を目安に積立しておくと安心です。
医療費積立の具体的な方法:安心の未来を築く戦略
医療費積立は、計画的に資金を準備することが重要です。医療費積立には複数の方法があり、個人の状況に合わせて適切な方法を選択する必要があります。
銀行預金による積立
最も基本的な方法は、銀行の定期預金や普通預金を活用することです。月々一定額を自動で振り替える仕組みを作ることで、継続的に医療費のための資金を蓄積できます。
1ヶ月で使わなかった医療費を翌月に繰り越すなど、無駄遣いを防ぐ工夫も効果的です。
保険商品の活用
医療保険は医療費積立の重要な選択肢の一つです。医療保険には入院給付金や手術給付金など、一時的な支払いが多くなる費用をカバーする特約が含まれています。
とくに先進医療特約や重大疾病保障特約は、高額な医療費が発生した際に大きな助けとなります。保険料は年齢とともに上がっていくため、若いうちに加入すると支払い額を低く抑えられるため、加入時期は慎重に見定めましょう。
医療費が高額になった場合の公的支援制度も知っておこう
突然の入院などによって医療費が高額になるケースにおいて、公的支援制度が使えます。こちらで紹介する制度を適切に活用することで、医療費負担を大幅に軽減できるので、事前に情報を調べておきましょう。
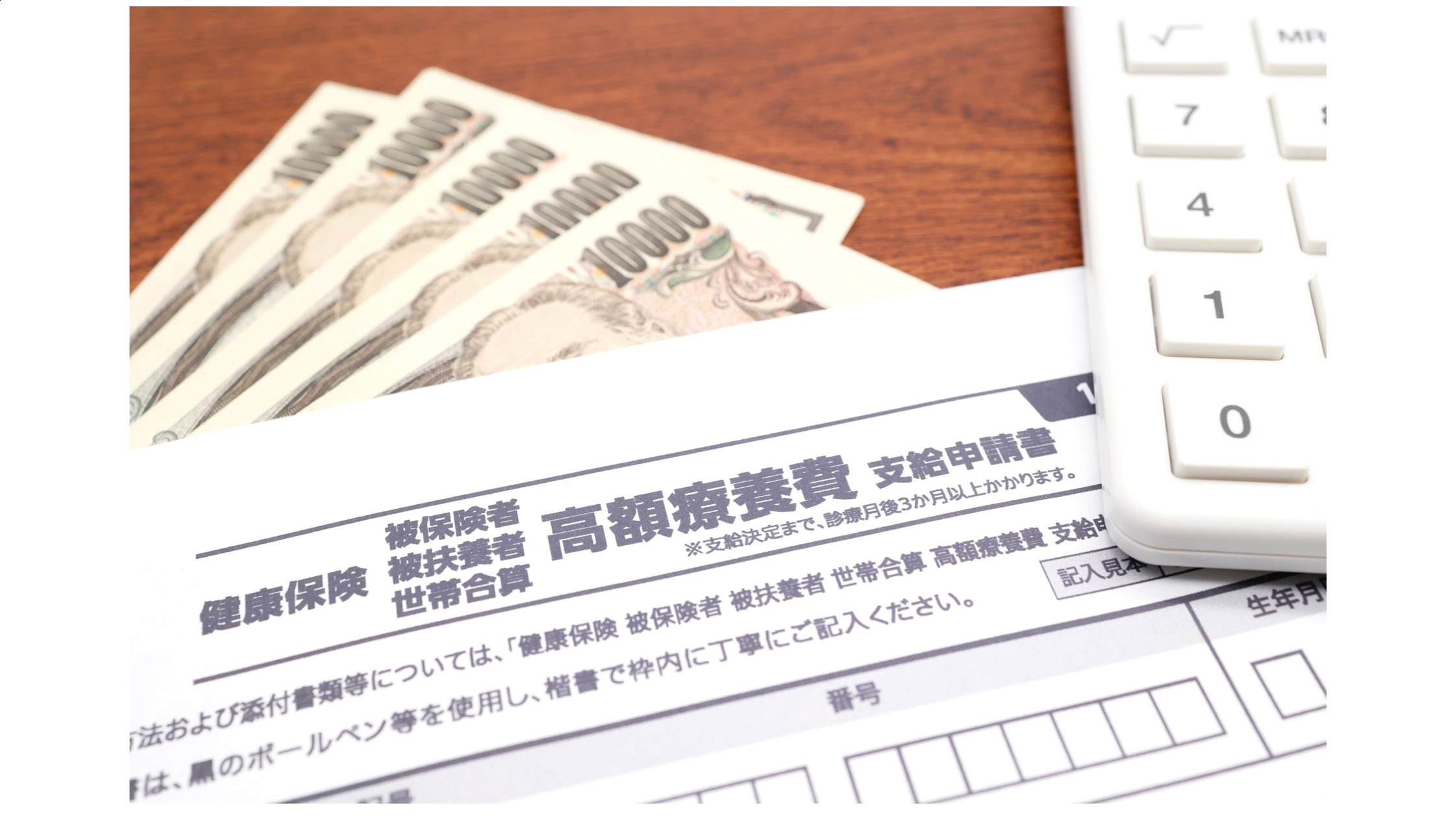
高額療養費制度
高額療養費制度は、月の医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合に、払いすぎた分が払い戻される制度のことです。
例えば、70歳未満の現役世代の場合、月の医療費が8万100円を超えるとその超過分が高額療養費として支給されます。
医療機関や健康保険組合が自動的に処理するため、手続きは最小限で済みます。しかしながら、入院などで医療費の支払いが増えることがわかっているときは、限度額適用認定証を申請しておくのがおすすめです。
医療機関での窓口の清算時に自己負担限度額までの支払いで済むため、必要以上に現金を支払う心配がなくなるからです。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やけがで働けない期間の所得を保障する制度です。健康保険に加入している会社員であれば、傷病手当金を受け取れます。
支給額は、直近12か月の標準報酬月額を基準に計算され、標準報酬月額の3分の2相当額となります。例えば、標準報酬月額が30万円の場合、1日あたり約6,000円が支給されます。
休業4日目から最長1年6か月まで支給されますので、長期で働けなくなった場合に助かる制度です。
まとめ
医療費積立は、毎年支払う医療費を先取りして貯蓄しておく家計管理の方法です。年齢や家族構成に応じて柔軟に計画を立て、銀行預金、保険など多様な方法を組み合わせることが重要です。
公的支援制度の理解を深め、長期的な視点で医療リスクに備えることが、安心で健康的な未来への鍵となります。




 人気ランキング
人気ランキング










 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



