金利が上がってきたことから変動金利の金融商品への関心が高まり、このコラムでは何度か「個人向け国債 変動10年」について紹介してきました。また、近年の物価上昇の下ではインフレヘッジ目的で注目が集まっています。日本の国債の中には、物価に連動する「物価連動国債」もあります。「物価連動国債」はどのような特徴なのか、概要をお伝えしましょう。
物価連動国債とは
物価連動国債は、物価の上昇率に応じて元金が増える国債で、10年前から個人投資家も購入できるようになっています。現在は年に4回のペースで、2月、5月、8月、11月に発行されています。これらは同じ年度内の発行であれば、どれも同じ銘柄として扱われ、10年後の3月10日が償還日です。
最低購入額面は10万円で、購入は額面10万円の整数倍です。発行価格は入札の結果によって決まる仕組みで、2025年11月18日発行の第30回(償還日は2035年3月10日)の発行価格は99円00銭。つまり、額面100万円を購入する場合の払込金額は99万円です。
物価を示す指標はさまざまありますが、物価連動国債が連動するのは「全国消費者物価指数(CPI)」から生鮮食品を除いた総合指数である「コアCPI」の動きです。生鮮食品は価格の変動が大きいため、生鮮食品を除いた「コアCPI」は物価の指標としてよく用いられています。
例えば、コアCPIが2%上がったとすると、物価連動国債の元金も2%上がります。コアCPIの変動に合わせて調整された物価連動国債の価格を、「想定元金額」といいます。仮に10年物の物価連動国債の発行時に100万円購入し、償還時の10年後にコアCPIが20%上昇したとします。この場合、償還時の元本は120万円になります。
物価連動国債は、元金だけでなく、利子も物価変動に連動して増減します。利払いは半年ごとで、利子の表面利率は10年間固定です。利率は固定ですが、物価に応じて「想定元金額」が変動するため、「利払日の想定元金額×表面利率」で求められる利子の金額は、利払いの都度変わるというわけです。
例えば、表面利率が3%の物価連動国債を100万円購入し、コアCPIが1%上昇した場合、想定元金額が101万円になり、半年分の利子は「101万円×3%×1/2(半年分のため)=15,150円(税引前)」となります。2%上昇した場合は「102万円×3%×1/2(半年分のため)=15,300円(税引前)」です【図】。
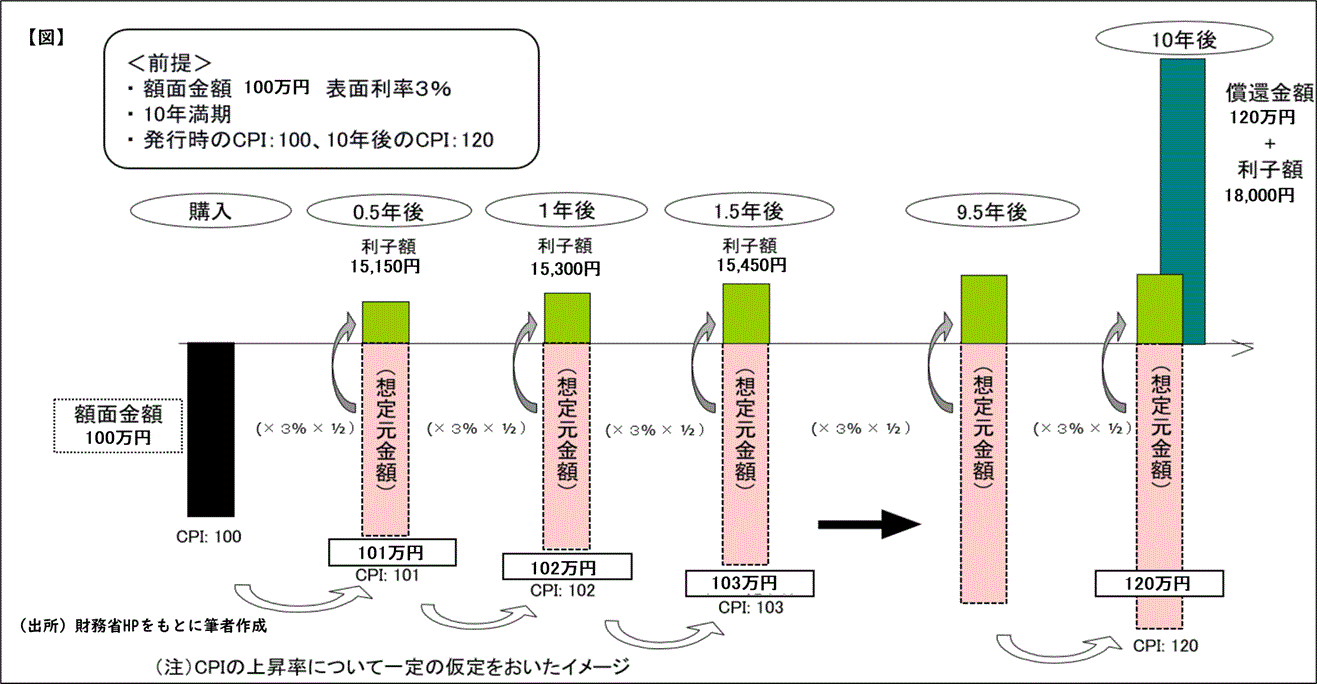
物価連動国債の販売窓口は証券会社ですが、取り扱いのない証券会社もあります。銀行では取り扱っていません。
物価連動国債は、償還時に元本が保証されている
物価連動国債は、保有期間中にデフレが進めば、想定元金額は元金である額面を割り込みます。しかし、物価連動国債には「元本保証(フロア)」がついており、償還時に限っては、コアCPIが下落していたとしても想定元金額が額面を下回らない仕組みになっています。
物価連動国債が日本に登場したのは2004年ですが、2008年に金融危機が起こった際、発行が停止されました。その後、先進国で物価連動国債が普及していたことから、日本でも2013年に再び発行されることになりましたが、当時の日本はまだデフレの真っ最中でした。物価に連動する金融商品に対してニーズが低い中での発行再開となったため、2013年以降に発行された物価連動国債には「元本保証(フロア)」をつけて、購入しやすいような設計となったのです。
ただし、発行価格は入札の結果によって決まる仕組みですから、額面100円以上で発行されることもあります。冒頭で紹介した2025年11月18日発行の第30回(2035年3月10日償還)は99円00銭で発行されています。フロアである100円で償還されると、額面あたり1円の利益になります。
物価の読みが外れると、フロア価格でも損失発生
一方、2024年度に発行した第29回債は、4回とも発行価格が額面以上で落札されました。2024年5月の発行価格は105円70銭、同年8月発行分は104円30銭、同年11月の発行価格は103円55銭、2025年2月の発行価格は102円55銭。いずれもフロアである100円では償還差損が発生します。
購入後、物価上昇が進み、想定元本額が上昇しているタイミングで売却または償還を迎えれば良いですが、物価が下落し、発行価格以下の想定元本やフロアでの償還となった場合の元本はマイナスになります。
途中で受け取る利子を積み上げたとしても、元金部分の値下がりが大きい場合、元本割れは起こります。
というのも、物価連動国債の表面利率は、同じ時期に発行された同じ年限の債券に比べて非常に低く設定されているからです。そもそも物価に連動して元金部分が上下する点が特徴であるため、利子の収入を投資の目的にしていないからです。
実際に、2021年度に発行された第26回債から2025年度に発行されている第30回債までの表面利率は、年0.005%となっています。市場が予想する物価上昇率よりもコアCPIの上昇率が低い場合は、通常の国債(固定金利型の新型個人向け国債)の方が投資利回りは有利になります。
このように、物価連動国債は名前の印象から注目を集めてはいるものの、商品設計や投資判断の側面では個人投資家が購入するにはややハードルが高いといえるかもしれません。もしも物価連動国債に投資したいのであれば、物価連動国債を投資対象にした投資信託を購入する方が無難かもしれません。
【関連サイト】物価連動国債(財務省)




 人気ランキング
人気ランキング











 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



