日本銀行は、2025年9月18日~19日に開かれた金融政策決定会合で、保有するETF(上場株式投資信託)とJ-REIT(上場不動産投資信託)を売却することを決定しました。
これで異次元の金融緩和政策はひと区切りを迎えました。そこでこの機会に、中央銀行が実施する金融政策の基本をご説明し、最近の日本の金融緩和政策について振り返ってみましょう。
中央銀行の役割と金融政策
金融政策とは、国の中央銀行が行う、その国の金融を適度な状態に保つための政策です。国ごとに目的や運用面でやや異なる部分はあるものの、金融市場で金利や通貨の量を調整し、最終的にその国の景気を安定させることが主な目的です。
中央銀行とは、日本であれば日本銀行(日銀)、米国の場合は連邦準備制度(Fed:Federal Reserve System)における連邦準備制度理事会(FRB:Federal Reserve Board of Governors)です。欧州の通貨ユーロ導入国は、一元的に欧州中央銀行(ECB:European Central Bank)が行っています。
中央銀行は、金融政策について定期的に話し合います。日銀では「金融政策決定会合」、FRBでは「連邦公開市場委員会(FOMC:Federal Open Market Committee)、ECBは「政策理事会」が政策決定の場になっています。
中央銀行の会合後は、金融政策や経済見通しなどが発表されます。その内容は、金融市場の関係者や企業経営者から家計を担う個人に至るまでが注目しています。
日銀の金融政策は、「物価の安定」と「金融システムの安定」が目的です。日銀は政府から独立した立場で、政府から直接は指示されません。ただし、政府の経済政策と整合するように意思疎通を図っています。
「オペ」とは政策で国債などを売買すること
近年の日銀の金融政策の代表的な手段は、「公開市場操作(オペレーション、以下「オペ」)」と「政策金利の操作」が中心です。従来は「オペ」と「預金準備率操作」でしたが、2016年2月以降、「預金準備率操作」は行われていません。
「オペ」は金融政策の手段で、金融市場での国債などの売買です。オペの一環として、市場からETF(上場株式投資信託)やJ-REIT(上場不動産投資信託)を買入れる場合もあります。
日銀が金融機関などから国債などを買取る「買いオペ」では、日銀が金融機関に国債などの買付代金を支払います。金融機関は、お金を抱え込むより企業などに貸して利子を受け取る方が有利ですから、結果的に経済にお金が流れるという狙いで、景気を良くしたいときに行われます。
もう1つの代表的な手段「政策金利の操作」は、短期金利(無担保コールレート)の目標設定です。日銀と金融機関との間の貸付や預金の金利を操作し、経済への波及を調整します。
「異次元の金融緩和」を振り返る
ではここで、「異次元の金融緩和」について、簡単に振り返っておきましょう。
第二次安倍晋三政権による経済政策は、「アベノミクス」と呼ばれました。第二次安倍政権の発足は2012年12月。その後、2013年3月に黒田東彦氏が日銀総裁に就任しました。
同年4月、黒田総裁の初会合では、「量的・質的緩和」という政策を導入。金融政策の目標を「マネタリーベース」という世の中のお金の増加ペースに設定しました。なかなかデフレは止まらず、2016年には「質」と「量」のほかに「金利」も加えた「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」や、「イールドカーブ・コントロール」という、さらに新しい政策に踏み込みました。
「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」とは、金融機関が持つ日銀当座預金の一部にマイナス0.1%の金利を適用する政策です。「イールドカーブ・コントロール」は、国債の「買いオペ」を実施して10年国債金利をおおむね0%程度に誘導する政策です。
このように、黒田総裁時代の金融緩和政策は、異例の規模、手法、スピードで資産を買入れる政策で、「異次元の金融緩和」と呼ばれました。デフレ脱却と「2年で物価上昇率2%」を目標に掲げ、次々と打ち出した過去に例のない政策は、俗に「黒田バズーカ」と呼ばれています。
ETFやJ-REITの買入れ政策
じつは黒田総裁の就任前も、長期国債やETF、J-REITの買入政策を導入していました。日銀が初めてETFを買ったのは、白川総裁時代の2010年12月のことです。
この時は、期限を2011年12月までとし、TOPIXおよび日経225に連動するETFを上限4,500億円で買入れるという内容でした。
その後、黒田総裁にバトンが渡され、ETFの買入れは、対象銘柄を拡大したり、年間買入額の上限を増額したりして、規模を大きくしていきました。
2014年11月、買入対象にJPX日経400に連動するETFが追加されました。さらに2016年3月には、「設備投資および人材投資に積極的に取組んでいる企業を支援するためのETF」を新たな枠を設けて買入れることになりました。
2016年になると、ETFの買入れに関する政策は再三にわたり微調整され、この頃には、異次元の金融緩和の副作用などが指摘されるようにもなってきました。
そして、現在の植田和男総裁が就任して約1年が経った2024年3月、ETFの新規買入れを終了することとなります。
【グラフ1】は、日本銀行が保有するETFとJ-REITの残高(簿価ベース)の推移とETFに関する政策の主な転換点です。
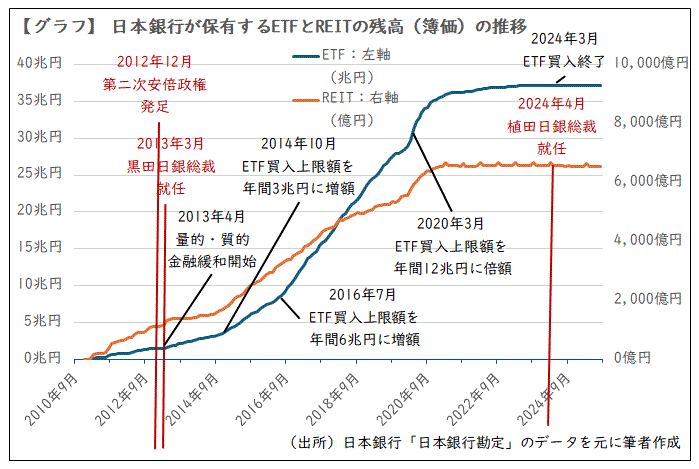
ETFやJ-REITを売り、金融政策の正常化へ
こうして買入れてきたETFとJ-REITが、今後、市場を通じて売却されることになりました。
日銀の売却方針によると、ETFは簿価ベースで年間3,300億円程度、各報道機関は時価を2025年3月末時点で6,200億円程度と計算しています。J-REITの売却は簿価ベースで年間50億円程度、報道では2025年3月末時点の時価換算で55億円程度とされています。
いずれも、東証の株式やREITの規模からすると、影響は軽微とみられています。「全部売却するのに100年かかる」というのは、一度に大量の売却をすると市場にショックを与えかねないので、少しずつ売るからです。また、市場の状況に応じて売却額の一時的な調整や、一時停止を行うなど、市場の安定に配慮するとのことです。
これでようやく、異次元の金融緩和政策は正常化への出口が見えました。今後は、売却のペースを市場に配慮しつつ調整しながら、金融政策の正常化を進めていくことになります。この動きが日本経済にどのような影響を与えるのか、引き続き注目が必要です。「トンネルを抜けると晴れていますように」と願うばかりです。




 人気ランキング
人気ランキング



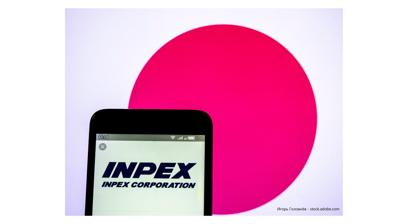







 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



