近年、資本効率に関する指標への関心が高まっています。資本効率を見る指標としてはROE(株主資本利益率)やROA(総資産利益率)が代表的ですが、ROIC(投下資本利益率)も脚光を浴びています。ROICとは、どのような指標で、どのように活用できるのでしょうか。
「ROIC」は「いくらつぎ込んで、いくら稼いだか」を見る指標
ROIC(Return On Invested Capital)は、「投下資本利益率」といい、事業につぎ込んだ資本で年間どれだけの利益を生んだかを示します。「資本をどれだけ効率的に活用して事業を行ったか」というリターンをベースにした収益の効率性で、経営者の視点での指標といえます。
事業につぎ込んだ資本を「投下資本」といいます。投下資本には、2つの着眼点があります。
1つは、投下資本を運用側から見るもので、「事業運営に使われている資産」の合計を投下資本とします。運転資本や固定資産をどのように使い、どのように稼いだかという見方です。運転資本は在庫や仕掛品などで、固定資産は工場や建物、機械などの設備です。これらの投下資本を用いて、どれだけ稼いだかに着目しています。
もう1つは、投下資本を調達側から見るものです。この場合の投下資本は、株主資本と銀行などから借り入れた有利子負債の合計です。事業につぎ込んだ資金でどれだけ稼いだかに着目します。
運用側に着目した投下資本と、調達側に着目した投下資本をそれぞれ貸借対照表で説明すると、【図1】に示すようなイメージになります。

「ROIC」は「ROE」や「ROA」とどう違う?
従来、資本効率を見る指標としては、ROE(Return On Equity:株主資本利益率)が主に使われていました。ROEもROICと同様に、事業につぎ込んだ資本から得られた年間の利益から算出しますが、「事業につぎ込んだ資本」の範囲が、株主が出資した分や株主に帰属する利益の蓄積分である点が異なります。
そのため、ROEは「株主が出した資本に対して、どれだけ稼いでくれたか」という見方になり、株主にとっての資本効率を測る指標といえます。ただし、株主資本を縮小すれば、利益額が同じでもROEは高くなります。このように、見かけの上で良い数字をだせる「ごまかし」ができてしまうところがROEの難点です。
一方でROICは、調達資金から得た本業の利益を測るため、見せかけに左右されにくいのが特徴です。
もう1つ、資本効率を見る指標としてはROA(Return On Assets:総資産利益率)があります。ROAは、「保有する資産を使って、どれだけ稼いだか」という指標です。ROAを算出する際の「保有する資産」は、貸借対照表の「総資産」で、株主資本と銀行などからの借入れのほか、取引先への買掛金なども含みます。つまり、事業に投下した資本だけでなく、その企業の資産全体から見た利益率ということです。
このような点から、ROEが株主の出資分に対する利益であるのに対し、ROAは企業の全体的な経営効率を見る指標といえます。銀行などの債権者や、自社の経営・財務部門、外部からの総合評価などにとっても、重視される指標といえるでしょう。
【図2】でROIC、ROE、ROAの違いをまとめました。
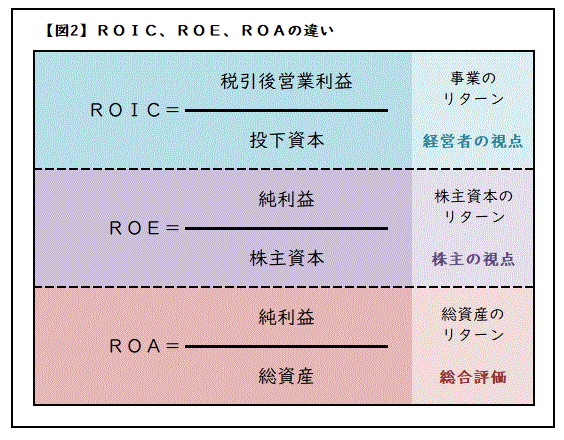
ROICが注目されている理由
ROICが優れているのは、事業ごとの資本効率を見ることができる点です。
設備や在庫といった投下資本は、事業ごとに管理されていることが多く、営業利益も多くの場合、事業部門ごとに算出されているため、それらのデータを使って事業別のROICを算出できるのです。
経営者としては、ステークホルダーから企業価値を高めることを求められ、好調な事業にはより成長のための投資をし、停滞している事業は縮小するという判断が必要になります。そのような場面で、事業ごとのROICが活用されています。
また、以前は、企業の評価は売上高や利益の増加が主な対象でしたが、近年は資本効率を重視するようになりました。政府や証券取引所からも企業の資本効率性を高めるよう要望されています。このような流れを受け、ROICを経営上の目標に掲げる企業が増えてきました。
決算資料や株主総会資料などでROICが取り上げられる機会が増えました。個人投資家でも、企業の本質的な競争力を見極めることができますので、ぜひ活用しましょう。
数年分のROICを見て、安定しているか、改善しているか、上昇傾向が続いているか、などのトレンドでの判断が重要です。企業が公表している資本コストと比べてROICが高ければ、その企業は価値を創造できていると見てよいでしょう。
他の指標と併せることで、総合的な投資判断に役立つのではないでしょうか。




 人気ランキング
人気ランキング












 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



