「金利のある世界」が戻ってきて、ますます個人向け国債「変動10年」の魅力が高まっています。2025年11月発行(募集期間:2025年11月7日~28日)の個人向け国債「変動10年(第188回)」の初回金利(2025年12月16日から2026年6月15日までの半年分)が、年利率1.10%に決まりました。
個人向け国債とは
個人向け国債は国債の一種で、財務省が毎月発行しています。「国債は国の借金」といわれますが、政府が行なう事業の重要な資金源です。公共サービスのために投資家が期限付きで国に貸す資金。期限が満了すると投資家に額面金額が償還されます。償還日までの間は年に2回の利子を受け取れるので、資産運用に利用されています。
個人向け国債は、通常の国債に比べて、個人投資家が利用しやすい設計です。販売窓口は銀行、証券会社などの金融機関。最低1万円から、1万円単位で購入できます。
個人向け国債の中途換金は、通常の国債と異なり、元本割れのリスクがありません。国が額面金額で買い取ります。ただし、発行後1年経過していなければ中途換金はできず、直前に受け取った2回分の手取利子が差し引かれるルールです。
この点をどう考えるか。「中途解約時はその前年の1年分の手取利子が差し引かれる」ということを短所と感じるか、「前年1年分の手取り利子さえ返上すれば、中途解約は可能」と長所ととらえるか、この見方の違いによって、投資するか否かを判断するとよいでしょう。
なお、災害救助法が適用される自然災害の被害者や死亡者は、発行後1年が経っていなくても中途換金が可能です。
個人向け国債は「固定3年」「固定5年」と「変動10年」の3種類
個人向け国債は、償還までの期限と金利タイプが異なる3種類があります。3年と5年は、発行時に決められた金利が償還まで続く固定金利。10年は、半年ごとの金利情勢によって利率が見直される変動金利です【表】。
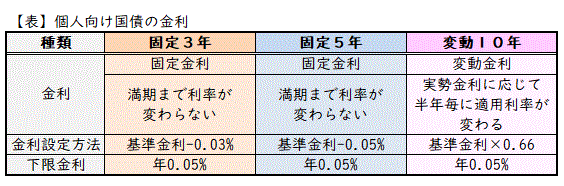
個人向け国債の金利は、「基準金利」を基に、市場の実勢金利によって決まります。
「固定3年」は「基準金利」から0.03%を引いた利率、「固定5年」は0.05%を引いた利率です。「基準金利」は、3年・5年のそれぞれの利付国債市場の利回りを基にして、募集期間開始の2営業日前に定められます。
「変動10年」の利率が決まるのは、利子計算期間が始まる約1ヵ月前です。適用利率は、「基準金利」に0.66を掛けた値。「基準金利」は、発行後最初の利子については募集期間開始日前の10年利付国債の平均落札利回りで、その後は半年ごとの利払期間の前月までの平均落札利回りを用います。
適用利率は、発表後半年間の利率です。例えば2025年12月15日までが募集期間の「変動10年」2025年11月債は、12月16日から2026年6月15日までが初回の利子計算期間で、2026年6月15日に1.1%(税引前)利子を受け取れます。
年利率1%台が定着してきた「変動10年」
変動金利は、「将来受け取れる金利が不確実」と考えるとデメリットですが、金利上昇のタイミングでは、受け取るたびに利子が増えるため、変動すること自体がメリットといえます。
【グラフ1】は「個人向け国債 変動10年」の基準金利と適用利率です。個人向け国債は毎月発行されていますので、発行債ごとの初回の適用利率も毎月発表されます。
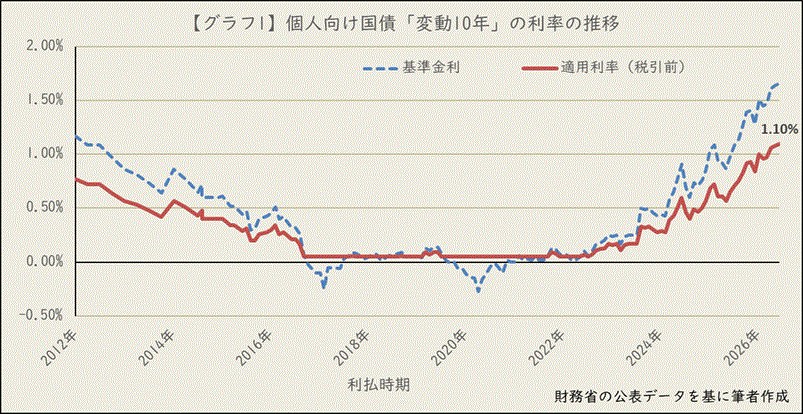
2011年6月までに発行された「変動10年」は利率の計算が現在とは異なります。現在の適用利率の計算式である「(基準金利)×0.66」になってからは、1%台は2026年1月利払分。その後いったん1%割れとなりましたが、再び2026年4月利払分が1.06%に。5月利払分が1.08%、6月の1.1%と3ヵ月連続で1%台に乗せてきました。
金利が上がれば利子が増える「変動10年」
では実際に、これまでの金利上昇局面では、どの程度の利子が受け取れたのでしょうか。過去の「変動10年」で計算してみましょう。
2026年6月15日に償還を迎える個人向け国債「変動10年(第74回債)」で確認しましょう。【グラフ2】の棒グラフは、10年間における半年ごとの税引後の受取利子です。赤い折れ線グラフがこの個人向け国債「変動10年」の適用利率で、青い折れ線グラフは基準金利です。

2024年3月に日本銀行の金融政策が転換して以後、市場金利が上昇し、半年ごとに適用利率が上がっています。
これに伴い利払金額も半年ごとに増加。発行直後の2018年までは100万円の額面に対して半年ごとに税引後約200円しか受け取れなかった利子が、最近では2023年12月に1,115円と千円台に。2024年6月には2,390円と倍増し、2024年12月に2,271円、2025年6月は2,589円の税引後利子を受け取れています。今後は2025年12月が3,346円、償還時の2026年6月には4,382円と決まっており、10年間の利子合計は、税引後2万円を超えることとなりました。
低金利でも個人向け国債の利子は相対的に有利
しかし、ここまでの説明では、「金利上昇局面だから良いかもしれないが、金利が低下すると適用利率も下がるだろう」と感じることでしょう。
いいえ、実は個人向け国債は3種類とも、冒頭の【表】中の「下限金利」欄の通り、利率の下限が年0.05%と決められています。じつは、これは低金利時に大きなメリットになります。
長く続いた国内のマイナス金利の下でも、個人向け国債の適用利率は年0.05%でした。他の金融商品より相対的に高い利回りが得られたのです。
【グラフ2】の2017年12月までや2019年12月・2020年6月の利払時は基準金利がマイナスでしたが、下限利率0.05%が適用されています。
資産形成の手段として、新しいNISA(少額投資非課税制度)が脚光を浴びていますが、NISAを利用するには、上場株式や株式投資信託を購入しなければなりません。資金の使い途や、ご本人の性格などから、これら以外の金融資産の方が適している場合もあるでしょう。
そのようなニーズに対しては、「個人向け国債 変動10年」が適しているといえます。
今後も「変動10年」の適用利率は、日銀の金融政策など金利動向の影響を受けます。さらなる利上げがあるかどうかは、国内の物価や景気、為替相場などにもよりますが、株式や株式投資信託は苦手だと考える人や、ポートフォリオ内で元本割れをしたくない資金の運用先として、選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。
【関連サイト】個人向け国債(財務省)




 人気ランキング
人気ランキング








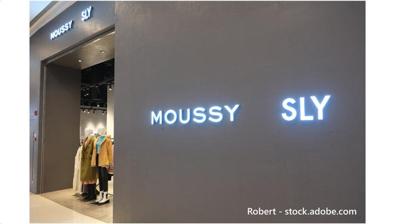



 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



