高市トレード、負の側面も見てみよう
自民党総裁選で勝利を収めて以来、世の中の高市氏に対する期待が高まったままです。
一部の市場調査では、8割を超す高支持率を確保しています。
積極財政だけではなく、保守層を取り込んでいることも支持率を高めています。
経済政策では高市政権は「地域未来戦略本部」を設置し民間からはリフレ派を起用しています。
「大胆な投資促進策とインフラ整備を一体的に講じる」と強調していることで、株価はうなぎ登りとなり、円安も進行したままです。
円安は株価上昇によるリスク選好も一因ですが、積極財政の負の側面が円安にもつながっている事実を無視してはいけません。
高市首相が所信表明演説で発言した「責任ある積極財政」ですが、残念ながら「責任ある」という言葉には疑問点があります。
先週まで行われていた衆院予算委員会で首相は「プライマリーバランス(PB)の見直しは、1月の中長期試算を見極め、6月に明確にする」と回答しています。
さらに、単年度のPBの黒字化を取り下げ、「数年単位のバランスを確認する」方針を示しています。
数年単位のバランスを黒字化するのではなく、あくまでも「確認する」だけです。
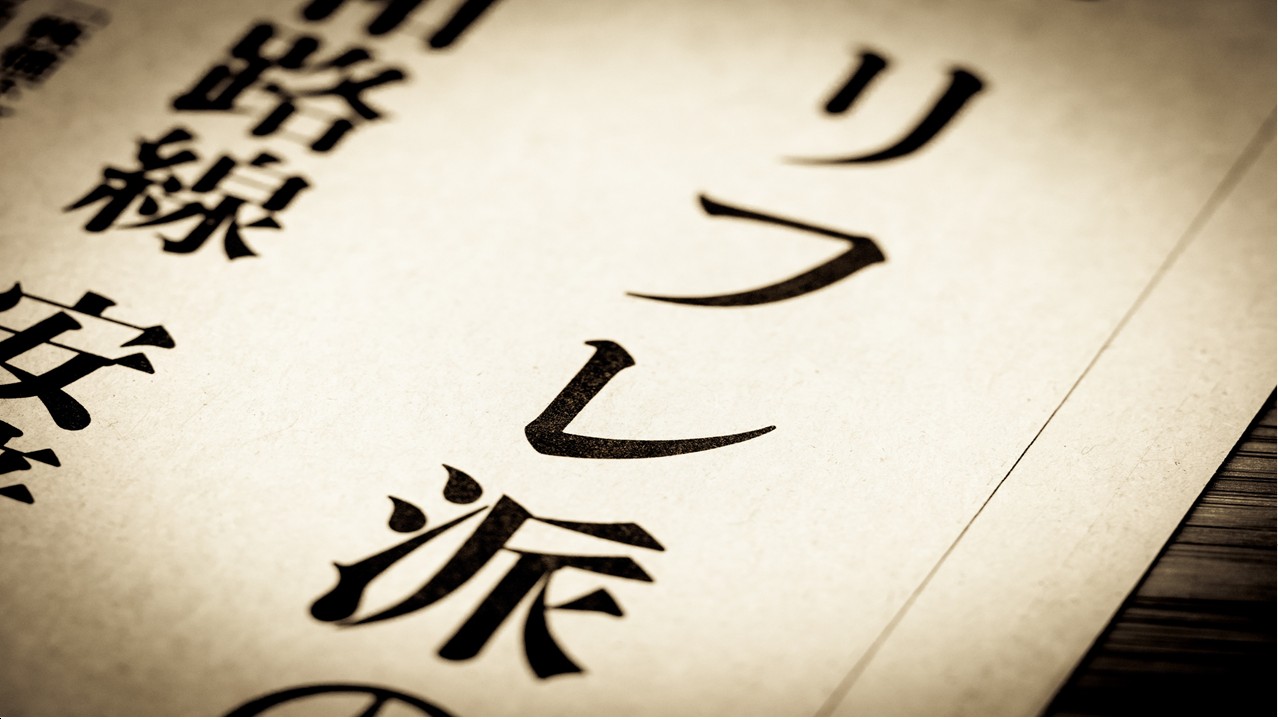
そもそも、日本は現時点でも純債務残高は比較可能な84カ国で最低水準です。
しかも、首相は「債務から年金積立金を差し引く経済協力開発機構(OECD)基準」に合わせようと目論んでいます。
年金積立金を債務返済に利用することはできないため、財政面ではさらに悪化することになります。
株高に対するリスク選好の円安ではなく、金融市場では財政悪化=放漫財政による負の側面でも円を売っているわけです。
日本と真逆の南ア、ランド円は2018年以来の高値更新
先週、ランド円が2018年以来となる9円台までランド高・円安が進みました。
この動きが如実に投資家の財政に対する見方を示しているといえます。
上述のように高市政権はPBバランスを無視した放漫財政の道を進んでいます。
補正予算が石破政権の13.9兆円を超える大規模予算になることが濃厚です。
城内成長戦略相も「高市首相は債務残高のGDP比引き下げを検討している」ことを明らかにし、国債の増発も排除しないことが伝わっています。
一方で、南アでは先週12日にゴドンワナ南ア財務相が中期予算声明(MTBPS=Medium-term Budget Policy Statement)を発表しました。
そこで、政府債務は2025-26年度にGDPの77.9%に安定することを示しています。
これは2008年の金融危機以来初めて、公的債務の比率が伸びないことを意味します。
財政赤字を2025-26年度のGDP比4.5%から2028-29年度は2.7%に縮小すると予想されています。
財政赤字縮小により南アの通貨ランドが買われ、放漫財政となる日本の通貨円が売られるという、ランド高・円安基調が鮮明に表れる結果になっています。
国内の高支持率と海外の株・円の評価は違う
このように、世界の金の流れという面では、放漫財政となる日本に対しては株は買えるが、円は買えない状況になっています。
また、アベノミクスの時と日本経済や金融情勢が違っています。
アベノミクス時は日本はデフレで困難な状況にあり、円高でも苦しんでいました。
今は全くの逆です。
高市首相は「デフレ脱却宣言には至らない」と述べ、「消費者物価(CPI)3%程度の上昇は食品高によるもの」と発言しています。
たしかに、食料品価格は上昇していますが、生鮮食料品を除いたCPIが昨年12月から7月まで3%を超えていたことを考慮すると、首相の発言は正しいとは言えません。
また、片山財務相も「日銀には安定的・持続的に2%程度のインフレが定着する状況を期待」と述べています。
しかし、本邦のCPIは総合、コア(生鮮食品を除く総合)共に2022年以後継続して2%を上回っています。
財務相発言に関しても整合性が合いません。
一部ではこのような発言をするのは、政権が日銀の利上げをけん制しようとしていると受け止めています。
首相が掲げていた食品に対する消費税をゼロにするという方針も撤回しようとし、参院選の敗戦を理由に国民当たり2万円の支給も中止していることで、株を持っていない国民の不満が出てきています。
しかしながら、高市政権は高支持率を維持していることで、高市政権は今後も放漫財政を継続していくことでしょう。
国内の支持率が高くても、金融界、特に海外投資家などは放漫財政に対する見方は厳しいということを理解しないでやってはいけないでしょう。




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング






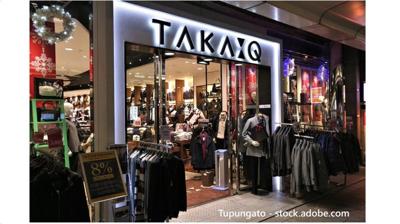













 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



