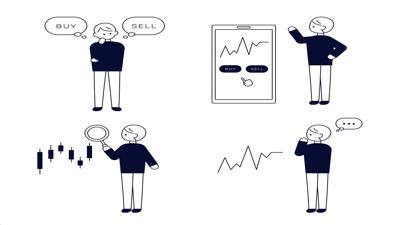今回解説していく通貨はドル円(usd/jpy)です。懸念されていた下降トレンド入りの可能性は否定され、年初来高値の更新に向けて底堅い地合いが継続することになりそうです。一方で、ファンダメンタルズ面では日米ともに金融政策に関して不透明感が広がっています。特に米国は政府機関が閉鎖されていた影響も考慮する必要があるでしょう。
今後のドル円相場の焦点:FRB議長は12月の利下げに対して慎重姿勢
まずは米国の現在の金融政策状況を確認していきます。
米連邦公開市場委員会(FOMC)は2022年3月に金融引き締めを開始。2023年7月に政策金利を5.25-5.50%まで引き上げて、2024年9月から金融緩和局面へと移行しました。現在の政策金利は3.75-4.00%です。
●FOMCが金利の引き下げを決めた10月直近会合での声明文では
・インフレ率は年初から上昇しており、依然としてやや高止まりしている
・委員会は2つの使命の両面に対するリスクを注視しており、ここ数カ月で雇用に対する下振れリスクが高まったと判断
・金融政策の適切な姿勢を評価するに当たり、委員会は今後もたらされる経済見通しに関する情報の意味を引き続き監視する
などの見解が示されました。
その後の記者会見でパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は「12月の利下げは決して確実ではない」と発言。FRB議長は政府機関閉鎖に伴って経済データが欠如した状況を「霧の中での運転」に例えるなど、慎重な姿勢を崩しませんでした。
12月FOMCでの利下げも規定路線としていた市場も軌道修正を迫られる格好となり、今後は遅れて発表される米経済指標をにらみながら、改めて米国の金融政策を探る必要があるでしょう。
ドル円 週足チャート分析:下降トレンド入りの可能性は否定
ではテクニカル面でも現在の状況を確認していきましょう。下図のチャートはドル円の週足チャートになります。

現在は2023年1月安値を始点とする上昇トレンド(チャート上の青色点線)が継続中。
今年1月につけた直近高値(チャート上の丸で囲った部分)が前回までの高値超えを果たせず、昨年7月高値を始点とする下降トレンド(チャート上の黄色実線)へと移行した可能性もありましたが、今月に入って上記トレンドラインを上方向にブレイク。下降トレンド入りの可能性は否定されました。
チャート下部に追加した「DMI」で確認しても、現状は+DI>-DI(上昇トレンド)を示唆。トレンドの強さを示すADXも上昇基調にあり、今後も上昇トレンドに沿った押し目買い方針が有効となるでしょう。
今後は今年1月につけた年初来の高値(チャート上の丸で囲った部分、158.87円)が上値の目標となりそうです。
ドル円 日足チャート分析:目先的な調整リスクも忘れずに
では短期的な視点でも今後のドル円の見通しを確認していきます。下図は日足のドル円チャートです。

現在は今年4月安値を始点とする上昇トレンド(チャート上の青色実線)内で推移しており、週足分析でも紹介した年初来高値の158.87円(チャート上の黄色実線)を視野に入れた動きとなっています。
もっとも、チャネルラインとの位置関係から考慮すると、現在の状況はかなり買われ過ぎに近い状況と見るべきかもしれません。年初来高値への到達予想時期(チャート上の線が交差したポイント)が来年2月以降となることもあり、目先的には調整リスクへの配慮も忘れずにしておきたいところです。
今後の取引材料・変動要因をチェック:10月分の米CPIや雇用統計は発表されない可能性も
最後に今後1カ月間の経済指標や重要イベント等も確認しておきます。注目は日米の金融政策。日銀は年内の追加利上げ観測も根強く残っており、米国と同様に金融政策に関しては慎重な見極めが必要となります。
また、米国では労働省が9月分の雇用統計を11月20日に発表すると公表。ここまでは政府機関の閉鎖前にデータの収集が済んでいたようですが、10月分の消費者物価指数(CPI)や雇用統計に関しては正確な結果が分からないとして当局者から指標の発表自体を行わない可能性も指摘されており、今後も政府閉鎖の影響による混乱は続くことが予想されます。
その他のイベントは以下の通りとなります。
今後1カ月の重要イベント
・11月20日 米国 9月米雇用統計
・11月21日 日本 10月全国消費者物価指数(CPI)
・11月26日 米国 10月個人消費支出(PCE)コア・デフレーター
・12月5日 米国 11月米雇用統計
・12月10日 米国 11月CPI
・12月9-10日 米国 米連邦公開市場委員会(FOMC)
・12月19日 日本 11月全国CPI
・12月18-19日 日本 日銀金融政策決定会合
米政府機関が閉鎖されていた影響で、一部の米経済指標は発表が前後する可能性があります
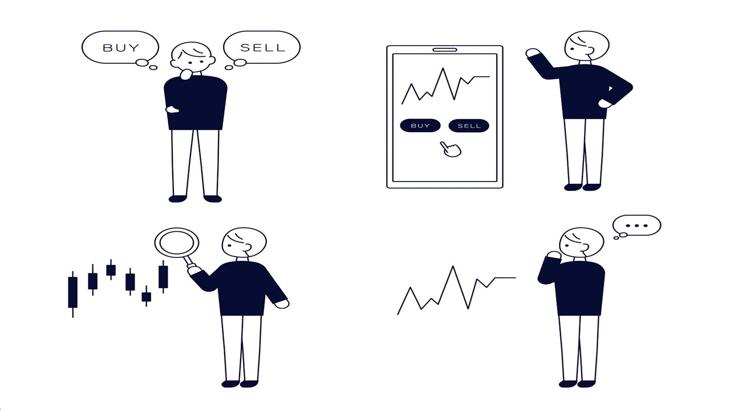



 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング







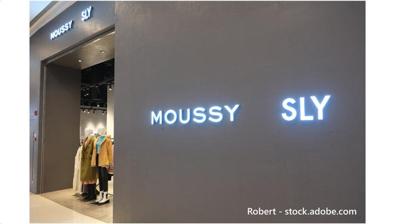













 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事