日本の家計部門が持つ金融資産残高が、2四半期ぶりに過去最高額を更新し、2,230兆円に達しました。リスク資産の値上がりに加え、規模は小さいながらも投資信託の継続的な購入が背景のようです。また、定期預金に預ける動きも出始めました。
ストック 家計の金融資産は、負債を差し引いた純資産も増加
日本銀行の「資金循環統計」では、3ヵ月ごとに、家計、企業、政府、海外部門の資金の流れと金融資産残高を集計し、公表しています。この統計での金融資産には、企業年金・国民年金基金等に関する年金受給権や、ゴルフ場預託金、個人事業主(個人企業)の事業性資金なども含まれます。
2024年12月末時点の残高は約2,230兆円(速報値)。9月末に比べて約50兆円増え、前年の12月末と比べると約86兆円増加しました【グラフ1】。
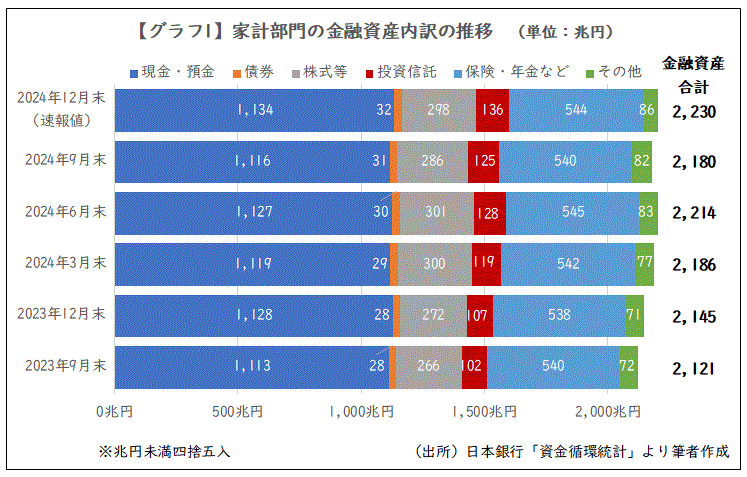
よく「日本の個人金融資産は、半分以上が現預金だ」と言われます。2024年12月末時点における現金・預金の残高は1,134兆円で、金融資産全体に占める割合は50.86%でした。残高は増えましたが、シェアでは前年同月の52.58%に比べて低下しています。
同様に、保険・年金なども残高は増加していますが、シェアは1年前の25.10%から24.41%に低下しました。
一方、前年末よりシェアが高まったのは証券投資。金融資産全体に占める割合は、債券が1.33%から1.43%へ、株式等が12.69%から13.36%へ、投資信託が4.97%から6.08%になりました。
ただし、証券は資産価値が上下するため、残高の増加は値上がりによる影響も受けます。株価上昇や円安が進行した時期ほど、これらの残高が増えています。2024年10~12月期の場合、株式等が14兆円分、投資信託が8兆円分、値上がりによってそれぞれ残高を押し上げました。
【グラフ2】は、データをさかのぼることができる1997年12月末からの株式等と投資信託の残高推移です。リーマン・ショック(2008年9月)ごろからアベノミクス前夜(2012年12月)までは低迷しています。
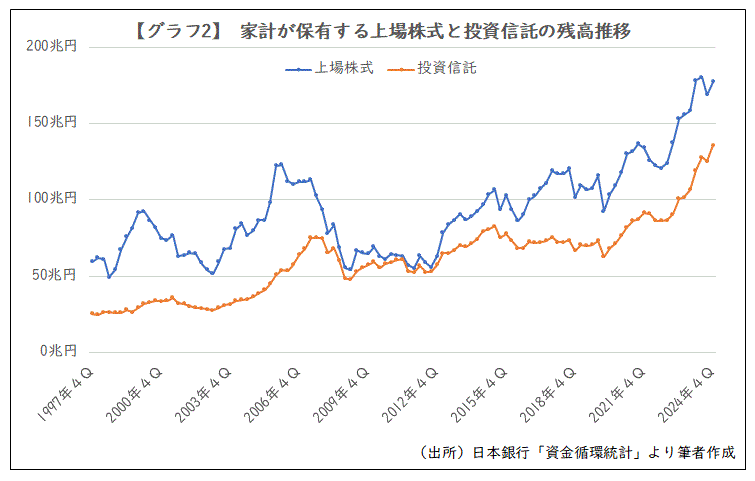
家計のお金は、貯めるだけではなく借りてもいます。家計部門の金融資産から金融負債を差し引いた「純資産」は、2024年12月末時点で1,834兆円。こちらも9月末に比べて約46兆円増加し、前年同月末と比べると約74兆円増えました。
定期預金の躍進
残高の増減は、価格変動のほかに資金の出入りも影響します。次は、金融商品に預け入れたり投資をしたりした金額から、解約や売却をした金額を差し引いた「資金フロー」について見ていきましょう。
10~12月期は冬のボーナスが支給される時期。家計は資金が流入超過になる傾向ですが、特に2024年の10~12月は、約20兆円という多額の純流入となりました。前年同期に比べて6割以上高い水準でした。
ところが、現金や普通預金などの流動性預金は、前年の同じ期間に比べて純流入額が細っているのです。3カ月間で現金は約2.8兆円の純流入でしたが、前年同期は約3.2兆円の純流入でした。普通預金などの流動性預金は約14.5兆円で、前年同期は約15.7兆円でした。
現金や普通預金に置いておかずに、他の金融商品に移している姿が浮かび上がります。
目についたのは、定期預金。2016年1~3月期から35四半期にわたって流出超過が続いていましたが、純流入に転換しました。2024年10~12月期まで純流出が続くと9年連続になるところでしたが、預金金利の上昇が歯止めをかけたようです【グラフ3】。
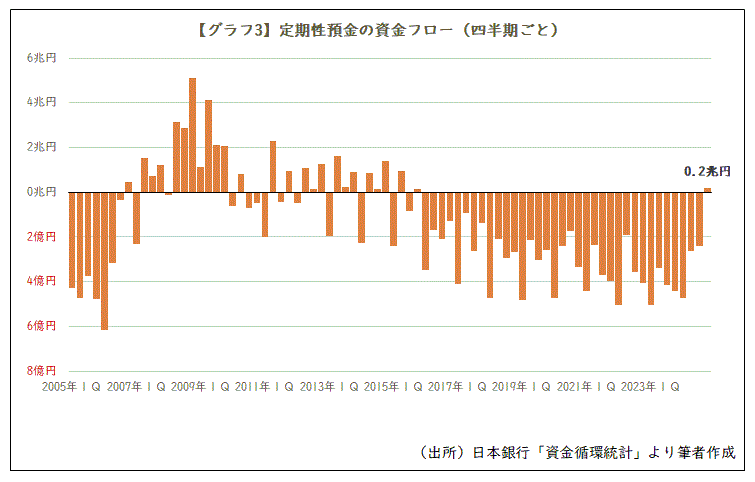
長期投資が根づくか、投資信託
また、全体に占める割合がさほど大きくないため目立ちにくいですが、投資信託の購入も増えています。2020年4~6月期から19期連続の純流入となりました。2024年の年間累計純流入額は11.6兆円。年間ベースで10兆円超の純流入は2007年の12.9兆円以来です。
なお、直近の投資信託の年間純流出入額は、2019年まで4年間純流出が続いて2020年に8,481億円の純流入に転じた後、2021年が6.0兆円、2022年が5.5兆円、2023年が4.8兆円のそれぞれ純流入という規模でした。2024年は投資信託の購入が急増したことがわかります。
投資信託の人気には、新しいNISA(少額投資非課税制度)が貢献していると推測しています。2024年は、日経平均株価が最高値を更新した瞬間があったり、円安が進行したりしたため、従来であれば、利益を確保する投資家も多かったことでしょう。また、夏以降の荒れた相場で不安になった投資家もいたと思われます。
そのような相場環境でも、投資信託が高水準の純流入となりました。資産形成への向き合い方に変化が感じられた2024年。今後、長期投資が根づくことに期待します。
【参考サイト】
●日本銀行>統計>資金循環




 人気ランキング
人気ランキング










 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



