iDeCo(個人型確定拠出年金)が浸透し、加入者の中にはそろそろ受け取りを考える年代の方もいらっしゃるでしょう。iDeCoは、受け取り方や受け取り開始時期などを自分で決めることができます。受け取り方を考える際のポイントについて、シリーズで解説していきます。第1回は「受け取り方の概要」です。
iDeCoの受け取り方は、さまざまな要素を考慮して決める
確定拠出年金制度が始まって20年以上が経ち、iDeCoの受け取り開始年齢が近づいている人が増えてきました。また、令和7年度税制改正や年金制度改正法が成立し、iDeCoの受け取り時期による税額の違いが話題に上るなど、iDeCoの受け取り方が注目されるようになってきました。
筆者も、「iDeCoはどのように受け取ったら有利ですか?」と聞かれることが増えました。これに一言で答えるのはとても難しいです。その方が何をもって「有利」と考えているかをしっかりお聞きしなければなりませんし、前提として、退職年齢や退職金の額、公的年金の受け取り額、再就職で収入を得るかどうかなどのライフプラン全体を踏まえて判断する必要があるからです。
さらに、iDeCoの運用対象として投資信託を選択していれば、換金するタイミングによって金額が変わります。受け取り開始直前まで投資信託で運用するのか、開始前に徐々にリスクを落として換金に備えるのかなど、運用面での戦略も考える必要があります。
また、今後も税制や年金制度が改正される可能性があるとすると、あまり早い時期に受け取り方法を決めなくてもよいのではないでしょうか。とはいえ、「若いからまだ受け取り方についての知識はなくても大丈夫」というわけでもありません。受け取る時の概要を理解しておきましょう。
老後のiDeCoは「一時金」「年金」「一時金+年金」の3通り
iDeCoの「老齢給付金」は、原則として60歳以降75歳までの好きなタイミングで受け取り始めることができます。原則60歳以降に受給権を取得し、75歳の誕生日の2日前までに請求手続きをします。手続きは、ウェブサイトかコールセンターを通して行います。
「老齢給付金」の受け取り方法には、一括で受け取る「一時金」と、分割受け取りの「年金」、そして「一時金と年金の組み合わせ」の3種類があります。この受け取り方法は、受け取りの請求をするときに選択します。
DCの「老齢給付金」は、個人型(iDeCo)も企業型も、受け取るときに、金額によっては税金が課せられます。受け取り方法が「一時金」であれば、所得税の「退職所得」という扱いになり、「年金」であれば「雑所得」という扱いになります。
「退職所得」と「雑所得」では、税金の計算方法が異なります。税金を計算する際のルールによって、税額に差が出るため、冒頭で紹介した「どのように受け取ったら有利ですか?」という質問になるわけです。
「老齢給付金」の受け取り方法と税金については、このシリーズ第2回目で詳しく説明します。
60歳になっても受け取れない場合
ただし、60歳に達しても「老齢給付金」を受け取れないケースが2つあります。
1つめは、60歳になっても掛金を積み立てている場合です。
iDeCoは、現行制度で65歳まで掛金を拠出できる人がいます。国民年金の「任意加入被保険者」といって、公的年金である国民年金の加入期間が少ないために、60歳を過ぎても任意に保険料を払っている人です。また、会社員などで厚生年金に加入して働き続けている人も、65歳に到達するまではiDeCoの積み立てを続けることができます。
これらの人は、積み立てを終了しなければ受け取り始めることができません。
もう1つの場合は、60歳の時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合です。
通算加入者等期間とは、iDeCoと企業型DCの加入者であった期間と積立を行わずに残高の運用指図を行っていた期間の合計です。ただし、60歳に到達した翌月以降の期間は合計しません。
通算加入者等期間が10年に満たない人の受け取り開始年齢は、【表1】の通りです。ただし、60歳以上で初めてiDeCoに加入した人は、加入から5年を経過した日から受け取ることができます。
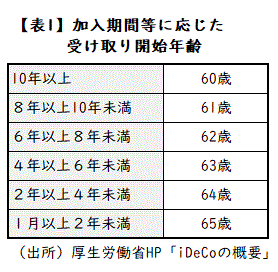
障害の状態になったときや加入者が死亡したときなど
iDeCoは老後の生活資金を目的にしていますが、60歳以降に受け取る「老齢給付金」のほかに、「障害給付金」「死亡一時金」「脱退一時金」があります。
障害給付金は、傷病等により政令に定める程度の障害の状態となった場合、裁定請求を行うことで、障害給付金として受け取ることができます。請求は75歳までです。
死亡一時金は、加入者が死亡した場合、遺族が裁定請求を行い遺族に支給されます。死亡した加入者が生前に死亡一時金の受取人の指定をしていた場合、受給の権利は指定された受取人が優先されます。指定がない場合には、法令に基づいた順位で受取人が決まります。
脱退一時金については、本来、確定拠出年金の資産は原則60歳になるまで引き出すことはできないものなのですが、一定の要件を満たせば、裁定請求を行い、脱退一時金を受け取ることになっています。
障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の受け取り方(給付)と受給要件等は【表2】の通りです。
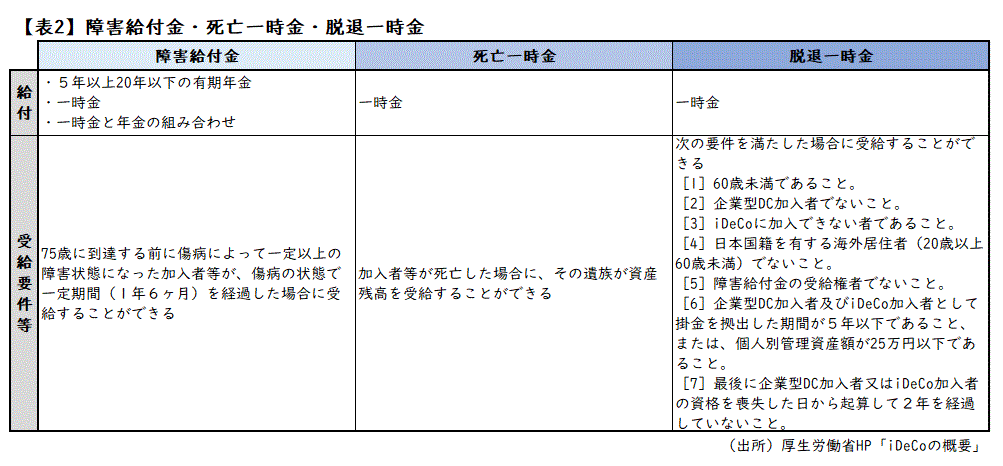
この「iDeCoのゴール設計図」シリーズの次回は、「②受け取り時の税金」について解説します。受け取り方法を検討する際のヒントとしてお役立てください。
【参考サイト】
厚生労働省『iDeCoの概要』




 人気ランキング
人気ランキング










 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



