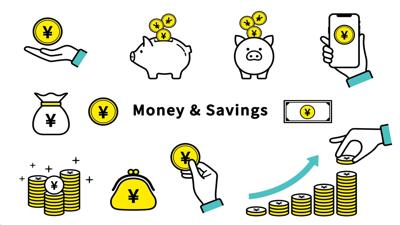2024年からの「新NISA(少額投資非課税制度)」は、それ以前のいわゆる「旧NISA」からは格段に使い勝手が良くなっています。とはいえ、利用者の利便性をさらに高めるための改善点も残されています。
そこで、今後のNISAがどのように改正されていくのか、令和8(2026)年度の税制改正要望をみてみましょう。
制度改正までの流れ
NISAだけでなく、私たちが守るべき法律やルールは、社会の変化に応じて国会で審議され、新たな法律ができたり改正されたりしています。それまでのステップの第一歩である「税制改正要望」は、各省庁が、8月末までに財務省(国税)と総務省(地方税)に提出します。
【図1】に税制改正のステップを簡単にまとめました。
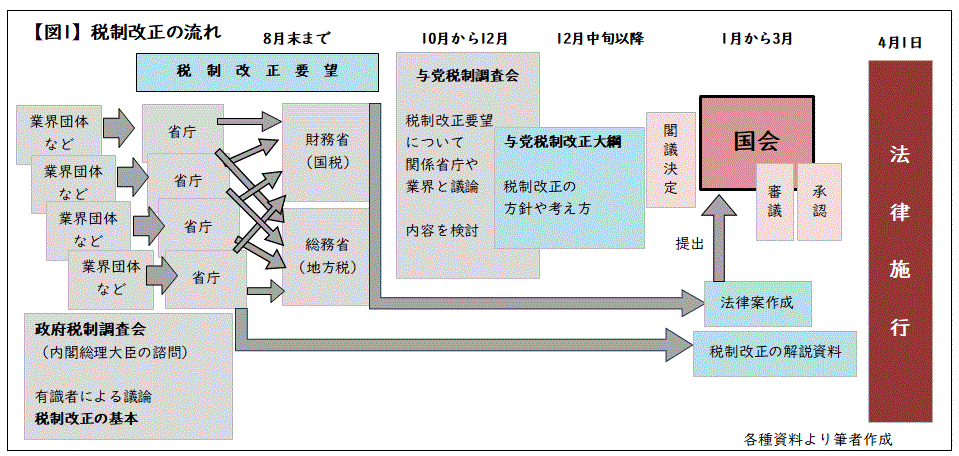
秋から年末にかけては、与党税制調査会と関係省庁との間で議論されます。12月に入ると大詰め。12月中旬から年末までには、与党内で決定した「税制改正大綱」が公表され、この時点で、ほぼ、国会での審議内容が決まります。その後、税制改正大綱は閣議決定となります。
税制改正大綱が公表されると、各省庁もわかりやすい解説資料を公表します。この解説は図表が多用されたわかりやすい資料で、各省庁のホームページから誰でも見ることができます。
税制改正大綱の内容に基づいて、国税は財務省が、地方税は総務省が、税制改正の法案を作成します。この法案が通常国会に提出され、審議・承認を経て法改正となります。
金融庁からの令和8(2026)年度の税制改正要望
では、金融庁の令和8(2025)年度の税制改正要望を見ていきましょう。
今回の要望の主な項目は、以下のとおりです。
1.「資産運用立国」の推進
・NISA対象商品の拡充を含む制度の充実
・NISAに係る所在地確認の手続きの簡素化等
・投資法人に係る税制優遇措置の見直し及び延長
2.暗号資産・保険
・暗号資産取引に係る課税の見直し
・生命保険料控除制度の拡充の恒久化
3.世界・アジアの国際金融ハブ」としての国際金融センター
・外国組合員に対する課税の特例の見直し
・クロスボーダー投資の活性化に向けた祖税条約等の手続きの見直し
・金融所得課税の一体化
このうちの『1.「資産運用立国」の推進』で挙げられている、NISAに関する部分についてみていきましょう。
金融庁によれば、現状のNISAは、若年層を含め、幅広い世代や所得階層にわたって利用が広がっているとのこと。あらゆる世代の長期・安定的な資産形成を支援するために、対象商品の拡充を含めたNISAの一層の充実を図る必要があるとしています。
要望の概要としては、
① こども支援の一環としての、つみたて投資枠における対象年齢等の見直し
② 様々な資産運用ニーズに応えるための、対象商品の拡充等
③ 投資商品の入れ替えをしやすくするための、非課税保有限度額の当年中の復活
と記されています。
日本証券業協会などの業界団体からも
税制改正要望は、省庁つまり行政機関から財務省への公式な要望です。他方で、業界団体からも「税制改正要望」が出されます。
日本証券業協会、投資信託協会、全国証券取引所協議会もNISAに関する税制改正要望を提出しています。これは民間団体による政策提言で、法的な手続きに基づくものではありません。ただし、与党税制調査会や金融庁・財務省への意見として、重要な役割を果たしています。
顧客や金融機関の事務手続きの負担軽減
令和7(2025)年度の税制改正でも、利便性の向上を目的として、金融機関の事務手続きの簡素化について要望が出されましたが、税制改正大綱では「あり方の検討を行う」にとどまっていました。
現行では、金融機関がNISA口座の顧客に対し、10年後などに郵送で所在地確認を行うことになっています。これでは顧客も金融機関も負担が大きいとして、改めて手続きの簡素化などを要望しました。NISA口座はマイナンバーと紐づけられているので、NISA口座開設者の所在地の把握は可能なはずです。所在地確認をデジタル化することで、金融機関の負担軽減および顧客の利便性向上につながるとしています。
対象年齢や非課税保有限度額、対象商品の見直し
現行制度では、NISAは国内に居住する18歳以上が利用できます。日本証券業協会、投資信託協会、全国証券取引所協議会の連名による改正案では、つみたて投資枠について、対象年齢を0歳からの居住者という要望をしています。
また非課税保有限度額について、現行では、ある年に売却した分は、翌年に限度額の枠が復活しますが、日本証券業協会等の改正案では、その年中に限度額の枠が復活するよう要望しています。短期売買につながる懸念もありますが、価格変動のある金融商品を柔軟に活用できるメリットもあります。
対象商品の拡充としては、日本証券業協会等の要望で下記【図2】が示されています。
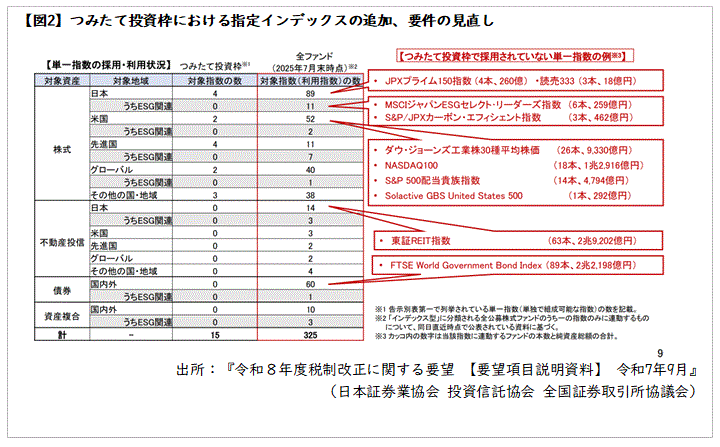
NYダウや東証REIT指数に連動するインデックスファンドが追加されれば、つみたて投資枠の幅が広がります。
「1人1口座」のルール撤廃は要望されず
ただ、今回も、同一年内のNISA口座の「1人1口座」ルールを撤廃する要望が出されなかったことは少し残念です。
銀行では株式を買えません。そのため、銀行でNISA口座を持つ人が株式投資をする場合は、証券会社の課税口座を利用しなければなりません。
また、投資信託は金融機関によって取扱商品が異なります。NISA口座を開設している人は、その金融機関で取り扱う投資信託しか選択できず、他社で取り扱う投資信託を購入したい場合、課税口座で買うことになります。
さらに、「1人1口座」のために、NISA口座が一握りの金融機関に集中していると感じます。投資信託を直販(直接販売)する運用会社の中には、とても魅力的な理念を掲げた会社が多いですが、自社の投資信託しか取り扱っていないことから、NISA口座として選ばれにくい傾向になっています。
税制改正要望の内容は、各業界団体などや各省庁のホームページで閲覧できます。報道機関も、要望の内容について識者の論説やその後の議論の経過を報じます。話題に上ると、決定事項と勘違いしてしまう人も見受けられますが、税制改正要望は、あくまでも「要望」です。各業界が「こうして欲しい」と要望し、法改正の案を作成に向けて準備するファーストステップです。その後の動向に注目することが大切です。
【参考】
「金融庁の令和8年度税制改正要望について」(金融庁)
「令和8年度税制改正に関する要望」(日本証券業協会)




 人気ランキング
人気ランキング












 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事