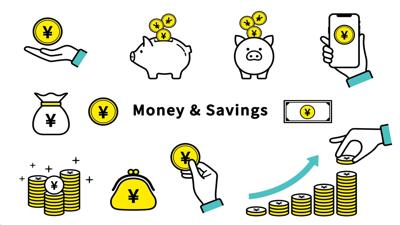旧NISA(少額投資非課税制度)の一般NISAで、2025年に5年目を迎えている株式や投資信託はありませんか?
以前のコラムでもご案内しましたが、年末が近づいてきたこの時期に、もう一度お知らせします。旧NISAの非課税期間が終了すると、翌年には課税口座に自動的に移管され、その後は課税口座での売却になります。
本コラムでは、非課税期間終了後に課税口座へ移管された後の売却と課税のルールについて解説しましょう。
NISA口座は、「1年ごとの引き出し」をイメージ
NISAの「非課税勘定」は、1年ごとの引き出しをイメージするとわかりやすいです。引き出しそれぞれに「2021年NISA」「2022年NISA」というラベルが貼られたキャビネットを想像してください。「2024年NISA」の引き出しは、それ以前より容量が大きくなりました。
2023年までの旧制度のNISAは、非課税期間が定められています。「一般NISA」は、買った年を1年目として5年目の年末までが非課税期間。年の途中に買ったとしても、受渡日が5年目の年末までなら売却益は非課税です。また、株主配当金や収益分配金も、5年目の年末までに受け取ったものが非課税の対象です。
同様に、非課税期間が20年の「つみたてNISA」も、積み立てた年をそれぞれ1年目として各20年目の年末までが非課税期間となります。
年末に非課税期間が満了すると、年明けから課税口座へ
通常、証券取引で利益が出た場合は、その利益に対して20.315%の税金が課されます。これが本来の「課税口座」での取引です。課税口座には「一般口座」と「特定口座」の2種類があります。課税口座についての詳しい解説は、以前の記事『証券税制の基本「一般口座」と「特定口座」』で説明していますので、ご覧ください。
「一般NISA」の5年目の年末や、「つみたてNISA」の20年目の年末が到来して非課税期間が満了すると、非課税期間が終了した引き出しだけ、ラベルが貼り替えられます。
「2021年NISA」の引き出しが「一般NISA」だったとすると、この引き出しは2026年からラベルが貼り替えられます。
NISA口座の取引金融機関に「特定口座」がある人はラベルが「特定口座」に貼り替えられ、「特定口座」がない人は「一般口座」のラベルに貼り替えられます。「一般口座」「特定口座」の両方を持っている人は、基本的には「特定口座」になりますが、申請によって「一般口座」への移管も可能です。
このラベル貼り替え作業は、「移管(払い出し)」といいます。
年末に非課税期間満了を迎えた引き出しは、年明けから課税口座として保管され、移管後に受け取る株主配当金や収益分配金は20.315%が源泉徴収されます(確定申告により清算可能)。
課税口座で持ち続ける場合の注意点
非課税期間が満了し課税口座に移管された後に売却すると、利益に対して20.315%が課税されます。
この課税口座に移管された時点で、取得価額(買値)はリセットされます。旧NISAで買った時の金額ではなく、「ラベルが貼り替えられた時点」の時価が買い値とみなされます。つまり、非課税期間最終年の年末の終値が、その後の課税口座での帳簿上の取得価額になります。
その後、課税口座で売る場合、「ラベルが貼り替えられた時点」と売却時の価格差に対する20.315%が税金として課されます。
ここで注意しておきたいのが、実際にNISA口座で買った金額は全く関係なくなってしまう点です。NISA内で値上がりした分には課税されませんが、課税口座になってからの値上がりに対して課税されるのです。
言葉で表すと単純に感じるかもしれませんが、値動きのパターンによっては、歓迎されないケースが出てきます。以下の4つのケースで見てみましょう。
いずれも、旧制度のNISA口座内で100万円の投資金額で買った上場株式が、非課税期間満了になって課税口座に移管されたとします。ここでは計算を簡略化するため、取引手数料は考慮していません。
【ケース1】NISA満了時120万円・課税口座にて135万円で売却
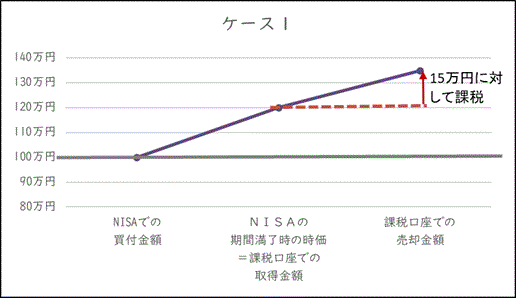
【ケース2】NISA満了時80万円・課税口座にて135万円で売却
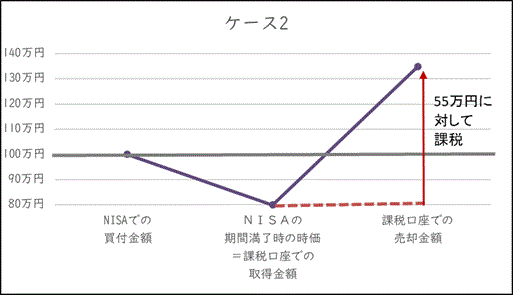
ケース1と2は、同じ135万円で売却し、当初の購入時からの利益が35万円でありながら、非課税期間満了時の価格の違いで、課税対象額が異なっています。ケース2は課税口座でのみなし取得金額が80万円であるため、差額の55万円に対して課税されてしまいます。
【ケース3】NISA満了時120万円・課税口座にて110万円で売却
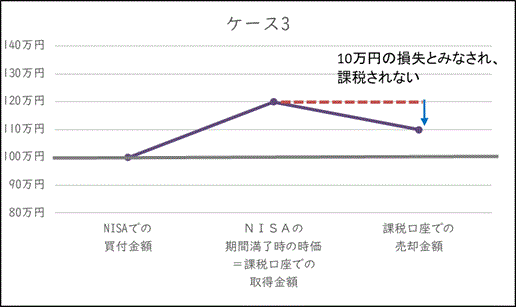
ケース3は、20万円の含み益がある状態で非課税期間が満了、課税口座に移管後、110万円で売却した場合です。
ケース1と同様、課税口座は120万円でスタートしましたが、ケース3は帳簿上で10万円の損失になりますので、課税されません。この投資家にとっては、NISAでの買付金額110万円から10万円の利益を上げていますが、帳簿上、課税口座では損失を出しているので、課税されません。なお、他に利益が出て売却した銘柄との損益通算もできます。
【ケース4】NISA満了時80万円・課税口座にて95万円で売却
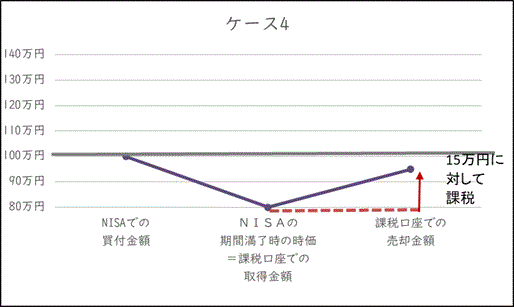
ケース4は、ケース2と同様、20万円の含み損を抱えて課税口座に移管。取得金額が80万円に引き下げられたため、95万円での売却は、当初の買付金額100万円からは損失にもかかわらず、帳簿上の差益15万円に対して20.315%が課税されます。
このように、旧制度のNISAの最終年の年末時価と課税口座での売却金額の関係によって、課税額が決まります。当初NISA口座で買った金額は関係ありません。ここでは「一般NISA」の5年後で説明しましたが、「つみたてNISA」の20年後も同じ考え方です。
2025年末には、2021年に購入した「一般NISA」が期限満了を迎えます。非課税期間中に売却するか、保有を継続して課税口座で保有するかは、銘柄の値動きやご自身の投資方針などを踏まえて、個別に判断すると良いでしょう。




 人気ランキング
人気ランキング









 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事