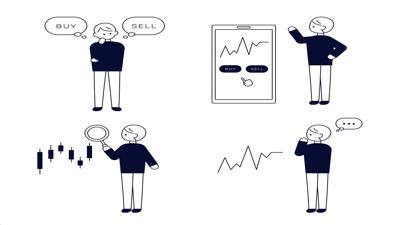今回解説していく通貨はトルコリラ円(try/jpy)です。依然として下落トレンドが続いている状況ですが、下げの勢いはやや和らぎつつある様子がうかがえます。短期目線ではレンジ相場となっており、目先はどちらにブレイクするか見極めたいところ。ファンダメンタルズ面ではトルコ中銀のインフレ目標達成が難しくなったことから、再び利上げに動く可能性にも警戒する必要があるでしょう。
今後のトルコリラ円の相場焦点:中銀が再び利上げへと転換する可能性も
まずはトルコの現在の金融政策状況を確認していきます。
トルコ中央銀行は2023年6月に金融引き締めを開始。2024年3月に政策金利を50.00%まで引き上げて、2024年12月から金融緩和局面へと移行しました。現在の政策金利は39.50%です。
●トルコ中銀が10月に金利引き下げを決めた直近会合での声明文では
・直近のデータは需要環境がディスインフレ的水準にあることを示す一方、ディスインフレの進行が減速していることも示唆
・物価安定が達成されるまで引き締め的スタンスを維持
・金利は会合ごとに慎重に見直し
・インフレ見通しが中間目標から大きく乖離した場合には追加的な引き締めも実施
などの見解が示されました。
トルコ中銀は四半期インフレ報告の中で、今年年末時点でのインフレ率を25-29%と予想。2026年末に16%、2027年末には9%に低下するとしていますが、足もとではトルコのインフレ鈍化傾向に陰りが見えてきており、市場では中銀の目標達成は難しくなったとの見方が広がっています。
そのため今後のインフレ動向次第では、中銀がインフレ抑制を狙って再び利上げに動くといったシナリオもあり得るでしょう。
トルコリラ円相場の週足分析:下落トレンド継続も、勢いは和らいだか
下図のチャートはトルコリラ円の週足チャートになります。現状は2021年に起きた急落が一巡した後、2022年4月高値を起点とした下落トレンド(チャート上の青色実線)が継続中です。

現状の下落トレンドから抜け出すには前述した下降トレンドラインをブレイクすることが必須要件。さらに昨年後半につけた直近高値(4.50-4.55円のゾーン、チャート上の四角で囲った分)も上抜ける必要があり、依然として高いハードルであることは間違いないようです。
ただ、チャート下部に追加した「DMI」で確認すると、現在は-DI>+DI(下落トレンド)を示唆しているものの、-DIと+DIが接近の気配を見せているほか、トレンドの強さを示すADXも足もとでは上昇基調が一服。下落トレンドも和らぎつつあることを示しています。
トルコリラ円相場の日足分析:目先は様子見姿勢、レンジ相場のブレイクを待つ
ここからは短期的な視点で詳しく見ていきます。下図はトルコリラ円の日足チャート(3日執筆時点)です。

年始からの下降トレンドラインド(チャート上の青色実線)は6月に入ってブレイク。ただ、その後も買い戻しは強まっておらず、現状は3.50-80円のレンジ相場(チャート上の四角で囲った分)に移行したと見てよいでしょう。「DMI」で確認しても6月以降は+DIと-DIが頻繁に交差しており、方向感を欠いた状況のようです。
ということであれば目先のトレードとしてはレンジ相場のブレイクを確認するまでは様子見でいるのが無難でしょうか。なお、レンジ上限の候補は6月16日高値の3.76円や5月12日高値の3.83円など。レンジ下限は7月24日安値の3.50円となります。
今後の取引材料・変動要因をチェック:トルコのインフレ動向に注意
最後に今後1カ月間の経済指標や重要イベントも確認しておきます。期間内には予定されていませんが、日銀は12月18-19日、トルコ中銀は12月11日に年内最後の金融政策公表が控えています。
前述したようにトルコではインフレの鈍化傾向に陰りが見え始めたことで、金融緩和方針に関しても先行き不透明感が浮上。今後のインフレ指標についてもしっかりと見極めていく必要があるでしょう。
その他のイベントは以下の通りとなります。
今後1カ月の重要イベント
・11月21日 日本 10月全国消費者物価指数(CPI)
・12月3日 トルコ 11月CPI




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング





















 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事