iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(確定拠出年金)は、受け取り方や受け取り開始時期などを自分で決めることができます。受け取り方を考える際のポイントについて、前回は「受け取り方の概要」についてお伝えしました。シリーズ第2回目の今回は「受け取り時の税金」です。
iDeCoの受け取り方で変わる“課税ベース”
前回のコラム「受け取り方の概要」では、DCの「老齢給付金」には、大きく分けて3パターンの受け取り方があるとお伝えしました。
一括で受け取る「一時金」と、分割受け取りの「年金」、そして「一時金と年金の組み合わせ」の3つです。本コラムでは、この受け取り方法の違いによって課税所得の計算が異なることを説明します。
DCの「老齢給付金」を「一時金」で受け取る場合は「退職所得」、「年金」であれば「雑所得」という所得区分になります。「退職所得」と「雑所得」では、税金の計算方法が異なります。
老齢給付金を「一時金」で受け取る場合
iDeCoや企業型DCを一時金で受け取る場合の「退職所得」の課税対象額は、同年に受け取った他の退職金などと合算され、原則として他の所得と分離して所得税額の計算をします。計算式は、以下の通りです。
[退職所得=(一時金の額-退職所得控除)×1/2]
退職所得控除は、DCの加入年数(企業型DCをiDeCoは合算できる)に応じて計算され、収入金額から差し引かれます。その後に2分の1を掛けるため、さらに税負担は軽くなります。
退職所得控除の計算は、DCの加入年数が20年以下の場合は「40万円×加入年数」で、20年超では「800万円+70万円×(加入年数-20年)」となります。20年超の計算式に使われている800万円は、「40万円×20年」のこと。この部分は「20年までは1年あたり40万円で、20年超は1年あたり70万円」をいいかえることができます。
加入年数の端数は切り上げ、1ヵ月でも1年として取り扱われます。退職所得控除額は【グラフ1】のように加入年数に応じて増加します。
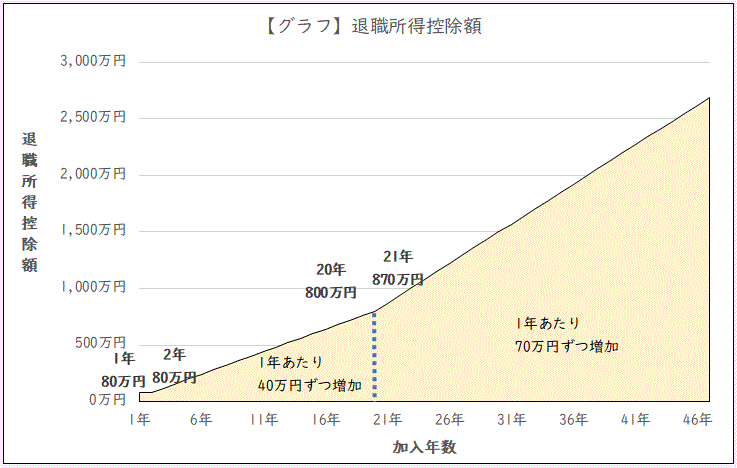
「一時金」で受け取る場合の税制面の注意点
ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、老齢給付金の一時金の金額に20.42%の税率を掛けた所得税(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます。
「退職所得の受給に関する申告書」は、DCの老齢給付の請求手続きの書類に同梱されています。特別な理由がない限り、記入して提出しましょう。提出しない場合は、受給者本人が退職所得の計算を行い、確定申告で税の精算をすることになります。
なお、ここまでの話はほかに受け取る会社の退職一時金などを考慮していません。現実的には、会社員などであれば退職一時金、規模企業の経営者や個人事業主であれば小規模企業共済の共済金(退職事由)などを受け取るケースが多いでしょう。
それらの退職金などとDCの老齢給付金をそれぞれいつ受け取るかによって、かかる税金が異なります。
それが巷でよくいわれる「5年ルール」や「20年ルール」です。法改正があり、注目を集めている話題の1つですが、これについては、このシリーズの第3回目に事例とともに詳しく説明することにします。
ここまでお伝えした、iDeCoや企業型DCの老齢給付金を一括で受け取る際の税金について、概要を以下の【表】にまとめました。
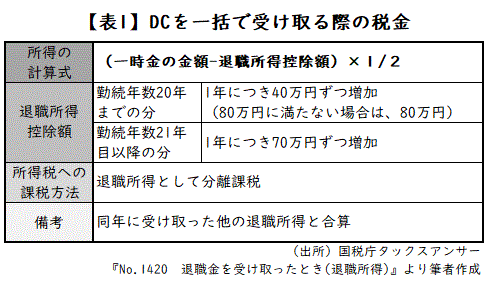
老齢給付金を「年金」で受け取る場合
次は、iDeCoや企業型DCを年金で受け取る場合です。所得の区分は「公的年金等の雑所得」という扱いで、総合課税になります。他の所得と合算され、各種所得控除(基礎控除等)を差し引いた後に、累進税率で課税されます。
[公的年金等の雑所得= 年金収入 - 公的年金等控除]
老齢給付金を年金で受け取ると、原則として「(年金収入-公的年金等控除)×5.105%」の源泉徴収が行われます。
公的年金等控除は、年齢と年金収入額で決まります。公的年金等以外の雑所得の合計所得金額が1,000万円未満の人の場合、65歳未満の人は60万円までは雑所得が0円です。65歳以上の人は110万円まで雑所得は0円です。
参考までに、公的年金等に係る雑所得の速算表を掲載しておきます【表2】。なお、公的年金等以外の雑所得の合計所得金額が1,000万円超の人は、別の速算表を使いますが、本コラムでは割愛しています。該当する方は、国税庁のHPや税務署等でご確認ください。
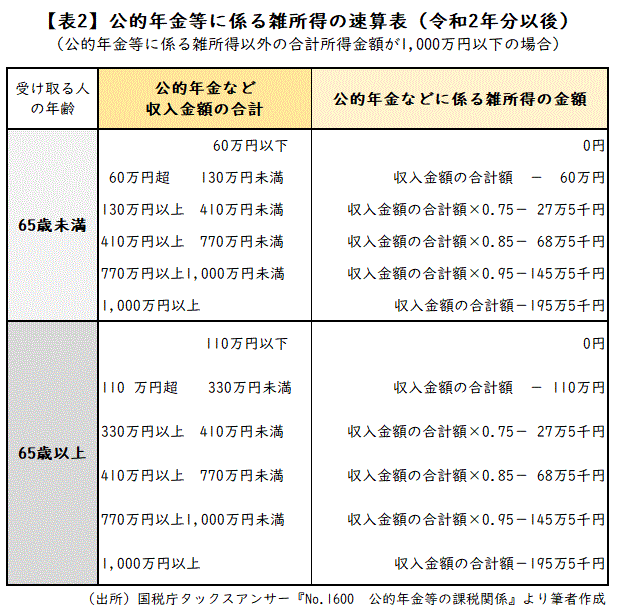
「年金」で受け取る場合の税制面の注意点
DCの老齢給付金を年金で受け取る場合、税制面では次のような注意点が挙げられます。
・一時金と違って、2分の1課税にはならない
・公的年金(国民年金や厚生年金など)と合算して課税される
・給与所得や事業所得などがあれば、合算されて累進課税となる
これらを考慮すると、他の所得が多い人は課税されたり税率が上がったりする可能性があります。年間の受け取り金額を抑えることで雑所得を少なくできますので、この点についても、後のコラムで丁寧に説明する予定です。
また、退職所得控除や公的年金等控除の金額や計算は、毎年の税制改正で変更される場合があります。最新の金額については、国税庁のホームページ等でご確認ください。
この「iDeCoのゴール設計図」シリーズは不定期ですが、次回は「③受け取り方の事例」について解説します。受け取り方法を検討する際のヒントとしてお役立てください。
【関連記事】
【参考サイト】
国税庁 タックスアンサー『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』
国税庁 タックスアンサー『No.1600 公的年金等の課税関係』




 人気ランキング
人気ランキング










 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



