2023年秋に導入されたインボイス制度。「中小企業の多くが潰れる」と懸念されながらも、制度開始から2年が経過しようとしています。国政選挙でもインボイス制度の反対が叫ばれているなか、制度を見直すという話は聞こえてきません。
消費税を納める義務は誰もがわかっています。最大の問題は免除制度があるなかで、「インボイス未登録企業の『不利益』は本当にあるのか」という点です。
登録は強制ではない
インボイス制度は消費税にかかわる仕組みです。年間売上1,000万円以下の事業者は、本来課税対象である消費税が免除されます。消費税は「受け取った(仮受)消費税から支払った(仮払)の消費税の差額」を支払うものです。つまり、会計期を通じてプールしておくべきものといえます。
中小企業にとって消費税分のプールはとても大変です。毎月のキャッシュフローをまわすために、これまでの消費税の免税措置はとてもありがたいものでした。消費税を減らすために「経費」でさまざまな購入を進め、仮払消費税を増やすのは一手ですが、キャッシュフロー上限界があります。
基本に立ち返ると、インボイス制度は「強制」ではありません。年間売上1,000万円以下の事業者は、これまでと変わりなく免税措置を適用することも可能です。ではなぜ反対運動が起きているのでしょうか。インボイス制度によって中小企業の倒産が危惧されるのは、登録をしないと「既存顧客から取引停止の可能性がある」ことによります。
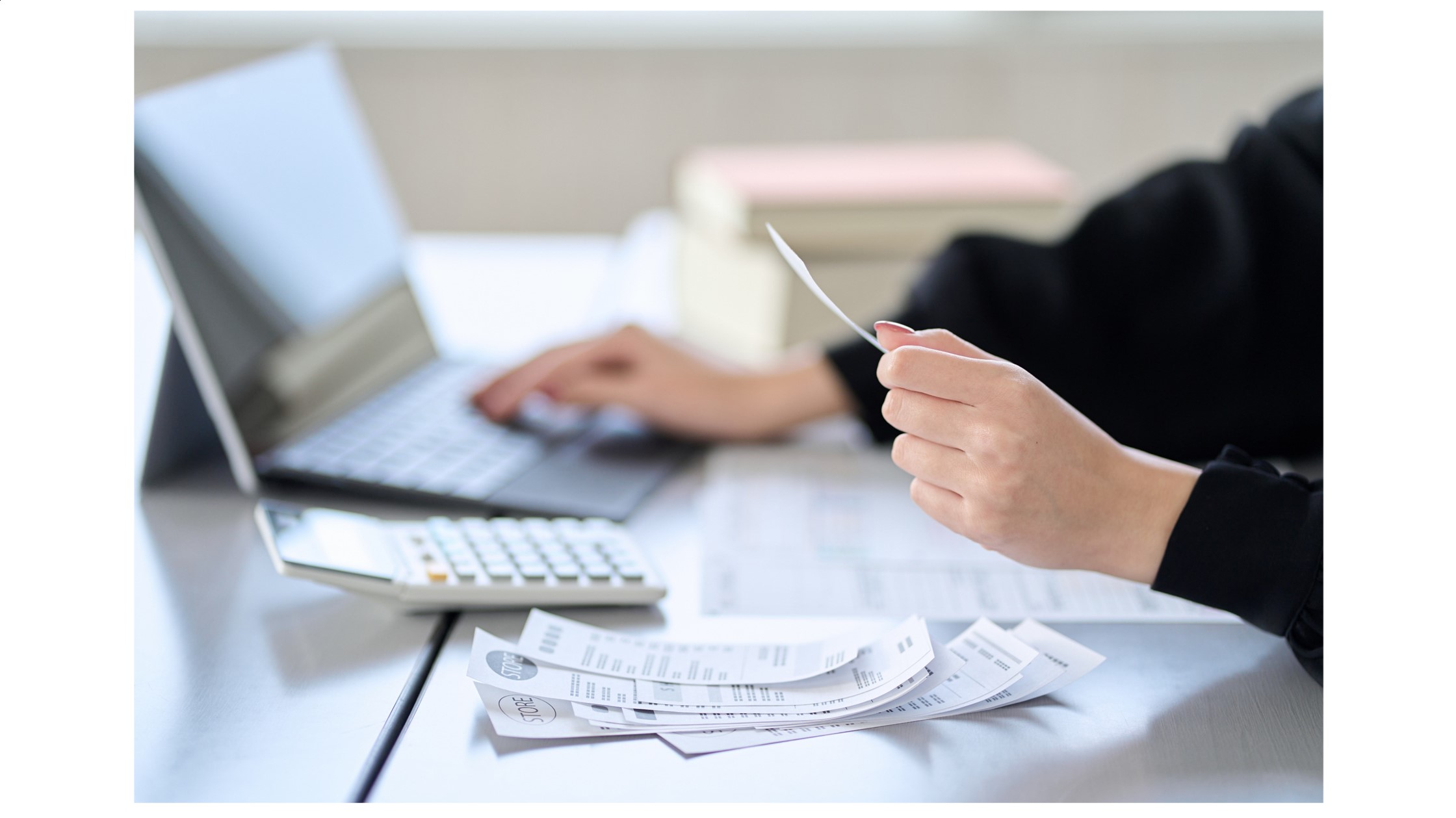
仕入額控除をどこまで重視するか
中小企業の「生殺与奪権」を握るインボイス制度をきっかけとした取引停止。その背景は、「免税事業者からの仕入れに対しては、買い主は仕入税額を受けることができない」というものです。
仕入税額控除を活用することにより、買い手は節税をすることができます。すると取引先に対して、「これまで通り、取引を継続したいならインボイスの登録を求めます」という姿勢へ転換する可能性があります。中小企業にとっては、このような姿勢を取る取引先が多ければ多いほど、インボイスへの登録を求められます。その代わりに、消費税の支払いが発生するという「どちらに行っても痛み」の仕組みです。
制度導入前に税務当局が「取引停止の可能性」まで想定していた可能性は低いです。ただ、実態として中小企業が消費税の納税か、もしくは取引停止のリスクが生じると判明した以上、何かしらのフォローが必要なのは間違いありません。
実際は2023年度税制改正によって制定された「2割特例」によって、売上時に受け取る消費税の2割だけ納税することが認められました。仮受→仮払ではなく、売上ベースの考え方が適用されます(2023年10月から2026年9月までの期間に会計期が含まれる場合のみ)。期限の終了については定められていますが、このような制度は世の中の動きを見ながら延長に次ぐ延長をすることも多いため、アップデートを怠らないようにしましょう。
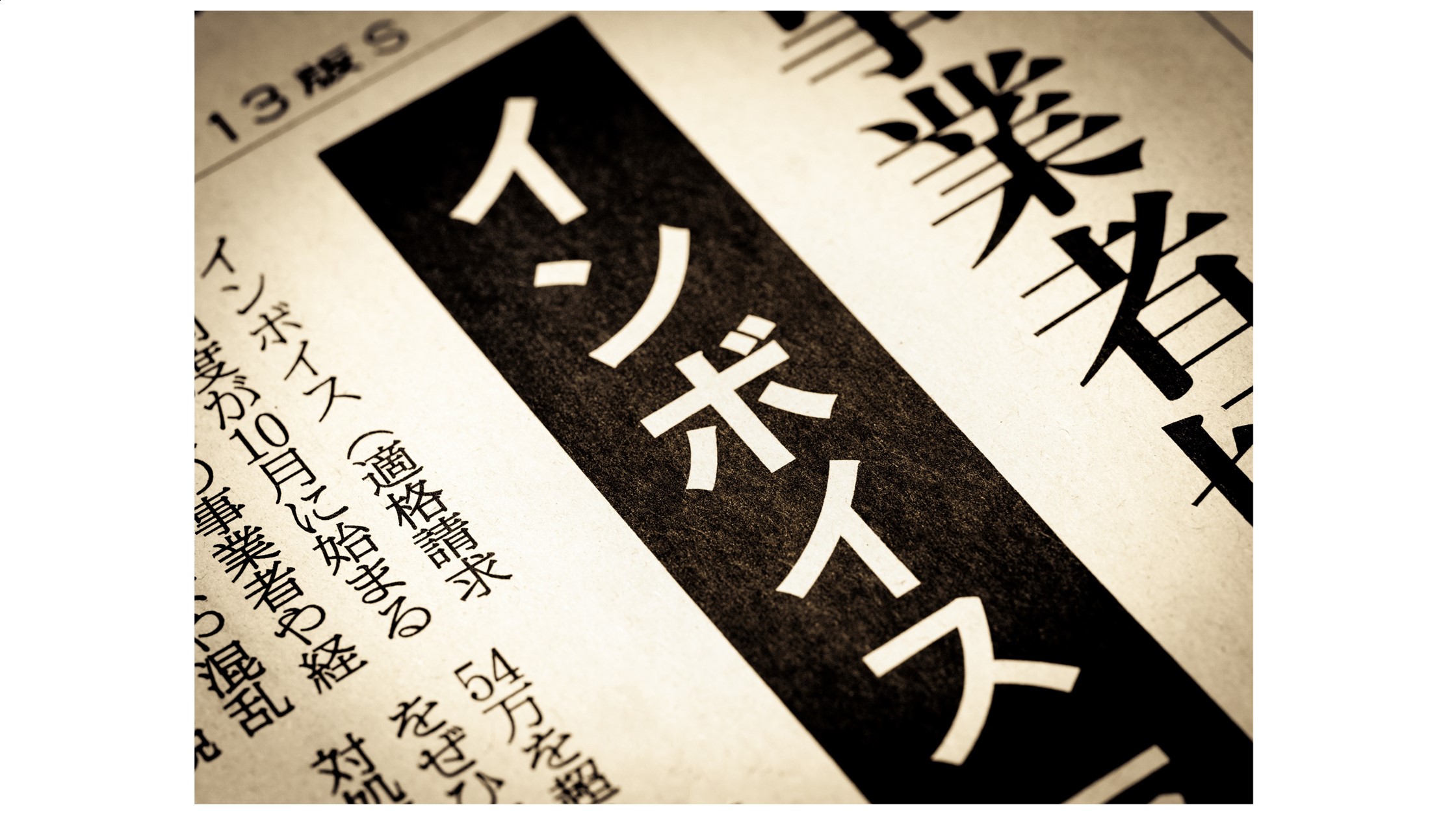
実際に「取引停止」はあるのか
実際に、インボイスで適格請求書を発行しないことによる「取引停止」のケースはあるのでしょうか。正直なところ、実態はわかりません。
国が統計を取っているものではないうえ、仮に仕入額控除が原因としても、「総合的な理由による契約更新をしない」と事実をオブラートに包むことは、いくらでもできるためです。特に上場会社であれば、インボイス未対応の取引先を「切っている」とは、口が裂けても言えないはずです。
問題なのは、それだけ悪用が想定されるインボイス制度を、消費税の確実な徴収とはいえ、導入が見直されない点です。この先2割加算を延長し、継続的なセーフティーネットを提供し続けることに効果はあります。ただ、「いつ終わるかもしれない制度」に頼らなければならない状況は、決して健全なものではありません。
取り急ぎできることは何か
では取り急ぎ、できることは何でしょうか。
(1)相手方の見解が聞けるなら尋ねる
取引をしているなら、濃淡あれど相手先とコミュニケーションが取れるはず。ある程度の関係性があれば、「インボイス登録しようか悩んでいるけれど、(仮に登録しなければ)取引は変わりますか?」と聞くのもひとつの方法です。100%本音とはわからずとも登録を推奨されなければ、年間売上1000万円まで免税事業者でいるのも可能です。幅広く案件を獲得しているわけではない中小企業の方には、特にお勧めできます。
(2)キャッシュフロー試算
2割特例の対象ならば支払う準備を整えることです。また月次(は無理でも四半期)でいま消費税はいくらなのか、管理することで不安感をコントロールすることができます。また1万円未満の取引には、インボイスが無くても帳簿を保存するだけで、消費税を控除することができるようになりました。このような小口取引や短期の費用送り、可能な限りの経費化に努めることが、事業者としての痛みの軽減に繋がります。
もちろん消費税が支払えるような状態になったら、きちんと支払うのが税金です。ただ、取引先との関係性を冷却化する現在の風潮は、とても問題であると思います。
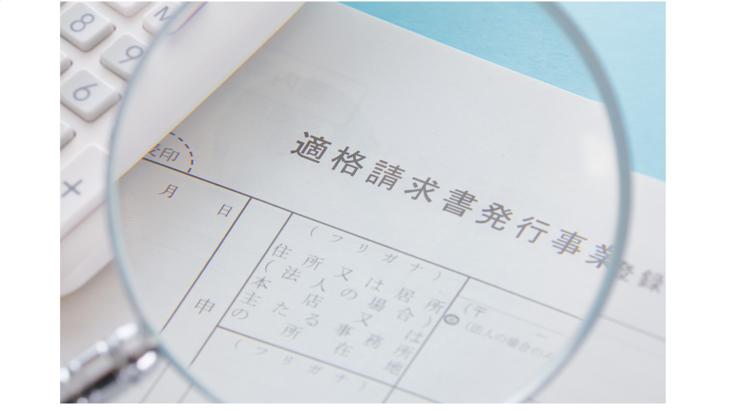



 人気ランキング
人気ランキング




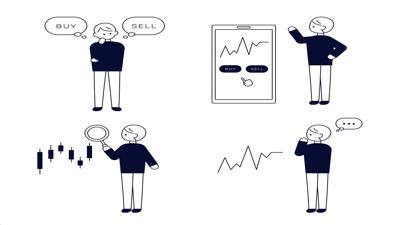







 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



