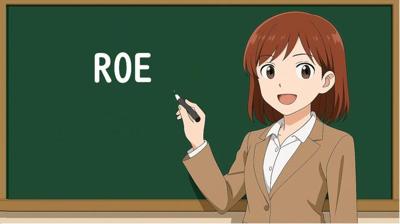インターネットやスマートフォンに囲まれて育ったZ世代。情報収集はSNSやショート動画が主流で、多様性を受け入れ、自分らしさを大切にすると言われています。
一般社団法人 投資信託協会は、Z世代のお金や生活の現状・考え方などについて、2024年10月下旬にインターネットで全国15 歳-34 歳の男女 3,000 人に対し、アンケート調査を行いました。
過半数が「お金について心配しない程度に平均的な生活を送りたい」
『投資信託に関するアンケート調査報告書-2024年(令和6年)Z世代調査』(一般社団法人 投資信託協会)では、調査対象者の15~34歳を「Z世代」とし、さらに15~24歳を「コアZ世代」、1990年代生まれを中心とした25~34歳を「初期Z世代」として分析しています。
Z世代の生活・お金等の価値観は、失敗を避けたい気持ちが強い、タイパ意識が高い、精神的なゆとりへの欲求が高く心理的な余裕を求める傾向とのこと。また、全体の55.6%が「お金について心配しない程度に平均的な生活を送りたい」そうです。より積極的な「他人よりもお金をできるだけ稼いで平均以上の生活を送りたい」と答えた人は、30.4%でした。
ポイ活やコスパ重視で節約して納得する買い物をしつつ、将来にも備え
【グラフ1】は、Z世代のお金についての考え方です。
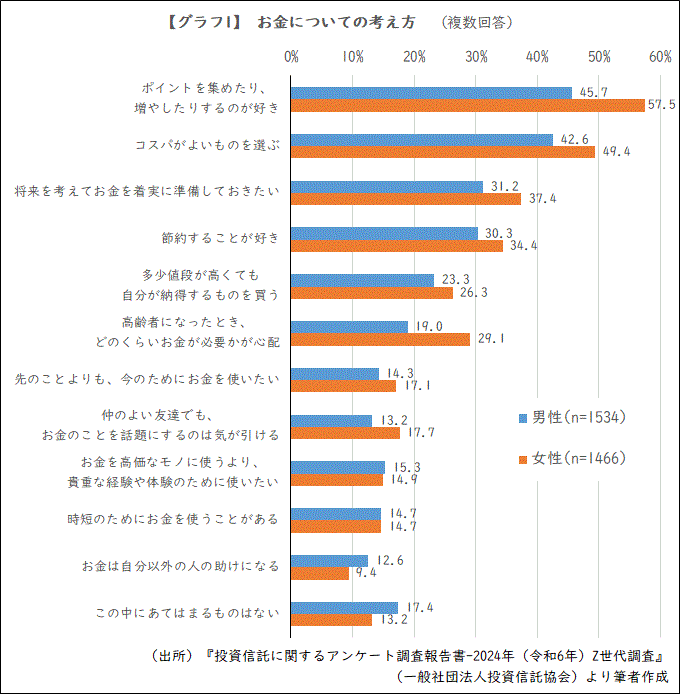
全体的に、女性の方が堅実的な印象です。特に、高齢者になったときのお金の心配については、女性が男性を約10ポイント上回るほど。現在の生活は、ポイ活やコスパ重視で、節約をしながらも納得のいくものを買い、一方で将来にも備えるという姿が浮かび上がります。
投資に興味がある人は、全体の半数に届かず
これらを踏まえると、効率よく将来に備えるために投資にも関心が向きそうですが、興味がある人は回答者の半数にも届きません。「とても興味がある」人が18.8%、「やや興味がある」は29.6%で合計48.4%、興味がない人は「あまり興味はない」が12.1%で「まったく興味はない」が22.8%の合計35.0%(四捨五入により合計は不一致)でした。
投資に対する興味は、男女差や世代による違いが見られます。「初期Z世代」や男性の方が、「コアZ世代」や女性よりも高い結果になりました【グラフ2】。
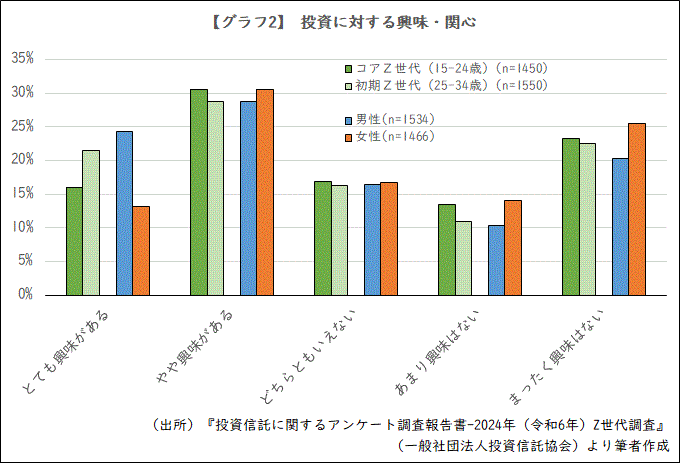
なお、冒頭で紹介した「他人よりもお金をできるだけ稼いで平均以上の生活を送りたい」人のうち66.1%が投資に興味があり、「お金について心配しない程度に平均的な生活を送りたい」人では46.5%でした。「お金は最低限確保できればよく、平均的に届かない生活でもよい」という人のうち投資に興味がある人は17.7%。お金と生活の考えに応じて投資への興味の度合いが鮮明です。
また、【グラフ2】で「先のことよりも、今のためにお金を使いたい」という310人のうち、投資に興味がある人は53.9%、「将来を考えてお金を着実に準備しておきたい」という867人の中では、64.4%が投資に興味があると答えました。「先のことより今」「将来を考えて準備」のどちらも選択しなかった人は、全体の55.4%に上る1,663人で、そのうちの42.7%は投資に興味がないようです。
お金に対して短期的に考えている人と長期的な視点の人では、一見すると対極ですが、どちらも投資への関心は比較的高いといえそうです。
興味がある人にとって、投資は「コツコツ」「難しい」「賢い感じ」
次は、投資に対する興味・関心の有無と投資のイメージについて見てみましょう。
投資のイメージを複数回答で聞いたところ、投資に興味がある1,453人の上位3回答は、「コツコツと積み上げてお金を増やす」(46.1%)、「難しい・勉強や知識が必要」(42.5%)、「賢い感じがする」31.2%でした。
一方、投資に興味がない1,049人の上位3つは「ギャンブル・賭け事のように感じる」(35.7%)、「難しい・勉強や知識が必要」(25.8%)、「お金が大きく減りそう」(23.0%)でした。
投資は難しく、勉強しなければならないというイメージは共通するものの、「賢い感じ」か「ギャンブル・賭け事のよう」かは、反対の印象です。金融リテラシーを身につけ、抱いているイメージや誤解を正しい知識や理解につなげる必要がありそうです。
金融リテラシーが低い人ほどリスキーな発想
最後は、ちょっと怖くなってしまった結果です。
この調査では、金融に関する質問によって調査対象者を金融リテラシーの水準別に分類しています。リスクや為替、物価、金利など9つの質問の正答率から、全体を「高リテラシー層(562人)、中間層(1,089人)、低リテラシー層(1,349人)に分け、他の質問とのクロス集計を行っています。
リスクに対する考え方については、低リテラシー層の極端な回答に驚かされました【グラフ3】。
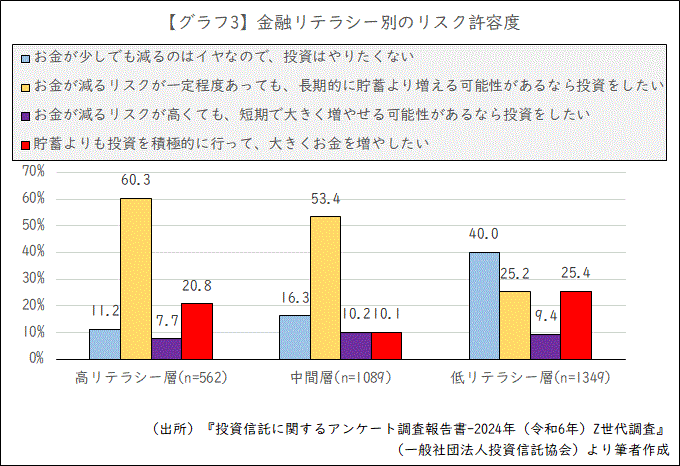
高リテラシー層や中間層では、投資のリスクをある程度許容し、長期的視点で投資をしたいと考える人が圧倒的。一方、低リテラシー層では、リスクを拒否する人が他より多いと同時に、短期の積極投資をしたい人も多いのです。「短期で大きく」と「投資を積極的に」を合計すると、低リテラシー層の3分の1を占めました。
「学校や会社の研修で教わりたい金融情報」として、複数回答で最も多かったのは「教わりたいことは特にない」で34.4%でした。大変残念な結果です。低リテラシー層の底上げができるような施策の必要性を感じました。
ほかの上位回答には「NISAや確定拠出年金などの税制優遇制度」(26.9%)、「投資・運用の仕組み・内容」(26.1%)、「ふるさと納税などの節税や税金」(23.8%)、「金融・経済の仕組み」(23.5%)、「ライフプラン」(21.5%)、「公的な社会保障制度の仕組み・内容」(21.0%)が並びます。教わりたいことが分散しているために、「特にない」がトップになってしまったのでしょう。
本調査では、情報源についても複数回答で尋ねています。普段の情報源はテレビが過半数で最多、投資の情報源として信頼できるものもテレビが2割強で最多でした。しかし、新聞・雑誌(7.3%)や企業の公式ホームページ(8.1%)より、Webのポータルサイト(13.4%)やYouTube(13.3%)、X(9.4%)が上回っています。
情報にあふれた環境で育ったZ世代ですが、投資をするなら情報の見極めも大切です。情報リテラシーを磨く必要性も感じます。個人的には、堅実で慎重なZ世代の特性を大切にしながら、失敗の経験から学ぶことも大事だと思っています。
【参照サイト】『投資信託に関するアンケート調査報告書-2024年(令和6年)Z世代調査』(一般社団法人 投資信託協会)




 人気ランキング
人気ランキング












 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事