iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(確定拠出年金)は、受け取り方や受け取り開始時期などを自分で決めることができます。受け取り方を考える際のポイントについて、シリーズで解説しています。
第1回は「①受け取り方の概要」、第2回は「②受け取り時の税金」についてお伝えしました。
第3回目の今回は「③一時金の受け取りと税金」です。受け取り方によっては税制優遇を十分に活かせない場合があるので、注意が必要です。
DCの一時金と退職一時金などを同じ年に受け取るとどうなるか
前回までに、DCの老齢給付金は、受け取り方によって所得税の所得区分が異なることや、それぞれの税金の制度についてお伝えしました。今回はその続きとして、DCを一時金で受け取る場合に、勤務先の退職一時金などとの関係で気をつけておきたい点について解説します。
退職所得は、iDeCoやDCのみならず、確定給付企業年金(DB)などの企業年金を一時金で受け取った場合も対象となります。同じ年に複数の退職所得があれば、それらの合計額に対して退職控除の枠を使い、枠を超えた分は課税対象となります。
iDeCoや企業型DCの老齢給付金は、60歳以降75歳までの好きなタイミングで受け取り始めることができます。特別な理由がない限り、勤務先の退職一時金などと同じ年に受け取らないようにするとよいでしょう。
退職所得控除“二重取り防止”のルール
では、iDeCoや企業年金の老齢給付金を受け取る時期は、1年でもずらせば良いのかというと、そう甘くはありません。いわゆる「5年ルール」や「20年ルール」があるからです。
これらは、iDeCoや企業年金の加入期間と、退職一時金を受け取る職場の勤務期間が重なっている場合に適用されるルールです。
これは退職所得控除額が不当に多額にならないようにするための措置で、たとえ老齢給付金と退職一時金を同じ年に受け取らなかったとしても、近い時期に複数の退職所得を受け取る場合には、退職所得控除額の計算上、重複期間に応じて控除が減額されます。
調整対象となるのは、原則は同じ年か「前年以前4年内」に受け取った退職所得の対象となる一時金ですが、DC(iDeCoと企業型DC)を受け取る場合に限り、さかのぼって調整される年数が異なります。
DCが先で退職一時金や他の企業年金などを後に受け取るのであれば原則通りですが、退職一時金や他の企業年金などが先でDCを後に受け取る場合には調整される期間が長くなります。理由は、DCは受取り期間を自分で選べるからです。
【1】iDeCoなどの一時金を先に受け取り、退職金を後で受け取る場合
ではまず原則通りの、iDeCoや企業年金などの一時金を先に受け取り、後に退職一時金や他の企業年金などを受け取るケースで見ていきましょう。
iDeCoや企業年金の加入期間と退職一時金を受け取る職場での勤務期間が重なっている場合、間に4年空いていなければ、退職一時金を受け取るときの退職所得控除が調整されます。重複期間は1年未満の端数は切り捨てて計算します。
退職所得控除は、前回の記事「②受け取り時の税金」で説明した通り、勤務(加入)年数に応じて計算されます。その際、重複期間を除いた年数を使います。
これについて、5年以上空ければ調整されないので「5年ルール」と呼ぶ人と、規定が「退職一時金を受け取る前年以前4年間」という表現のために「4年ルール」と呼ぶ人がいますが、どちらも同じことです。
なお、令和7年(2025年)度税制改正によって、2026年1月1日以後は「4年」が「9年」に拡大されます。つまり企業年金の受け取りから10年目以降であれば、重複期間の調整は行われません。
ここまで説明した原則と改正については、【図表1】の通りです。
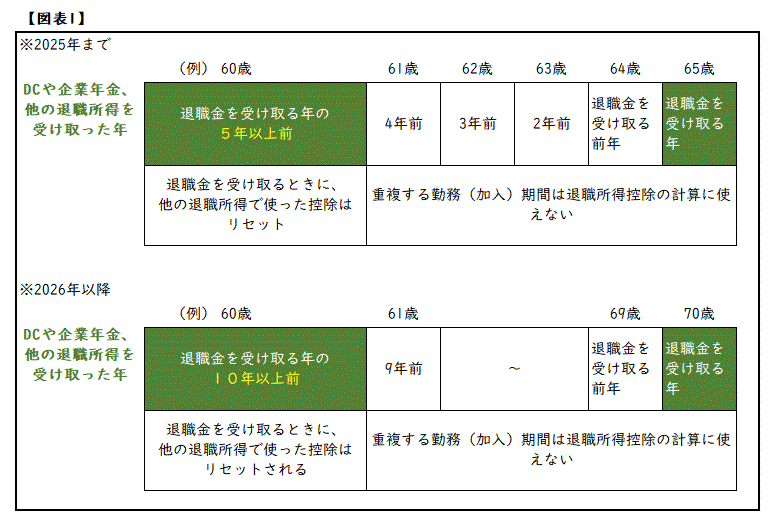
【2】退職金などを先に受け取り、後でDCの一時金を受け取る場合
次は、DC(iDeCoと企業型DC)を後で受け取るケースです。DCは受け取り時期を選ぶことができるため、簡単に複数回の退職所得控除を受けられないように設定されています。
DCの老齢給付の受け取り開始年齢は、2022年4月1日から75歳に延長されました。その際、退職所得控除の重複期間が調整される期間についても、DCの老齢給付を一時金で受け取る場合に限り「前年以前14年内」から「前年以前19年内」に改正されました。こちらは2026年以降も変わりません 【図表2】。
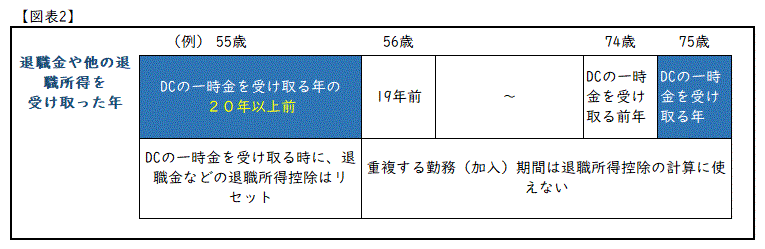
損か得かよりもライフプランを重視
ここまでは税制優遇に着目してきましたが、いつ退職するか、老齢給付金を何歳から受け取り始めるか、という問題は、誰にでも共通する正解はありません。一人ひとりのライフプランによって、最適な選択をすることが大前提です。
さらにいえば、税制面で有利か不利かを選択するよりも、何歳まで働くのか、セカンドライフのお金の使い方はどうなのか、といった点を考慮することが大切です。そのうえで、ある程度の選択の幅がある人にとっては、税制上のルールも参考にして受け取り時期を選ぶと良いでしょう。『iDeCoのゴール設計図』シリーズ4回目は、最終回として出口戦略のまとめについてお届けします。
【関連記事】
【参考サイト】
財務省 『令和7年度税制改正の大綱』
国税庁 タックスアンサー『No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)』




 人気ランキング
人気ランキング










 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



