中国Eコマース事業が中核、利益の95%稼ぐ
アリババ集団(09988)は、前回までに3回にわたってご紹介してきたテンセント(00700)と並ぶ、中国の代表的なインターネット企業です。両社はそろって1990年代後半に創業し、アリババが電子商取引(Eコマース)、テンセントがインスタントメッセンジャーを皮切りに幅広い分野でデジタル事業を展開するようになりました。
アリババの主力事業は現在でもEコマースです。中国で展開するオンラインショッピングモールの「天猫(Tモール)」や、CtoC(個人間取引)の「淘宝網(タオバオ)」などの「中国コマース小売り」が主力事業で、2025年3月期財務報告によると、売上高の41%、純利益の95%を稼いでいます。各プラットフォームを利用する企業・ブランドから受け取る販売手数料・取引手数料が主な収益源となっており、「Alimama」ブランドで展開するP4P(クリック課金型広告)、ディスプレイ広告などの広告・プロモーション業務でも収益を上げています。
海外でもEコマース事業を手掛けています。中国の中小事業者が世界の消費者に向けて販売できるオンライン小売プラットフォームの「アリエクスプレス(AliExpress)」、B2B(企業対企業)電子商取引市場をターゲットとしてグローバル展開する「アリババドットコム(Alibaba.com)」を運営しています。2010年代後半には東南アジアで事業展開するラザダ、トルコのファッションEコマース大手のトレンディオールを相次いで買収し、地域拠点としました。
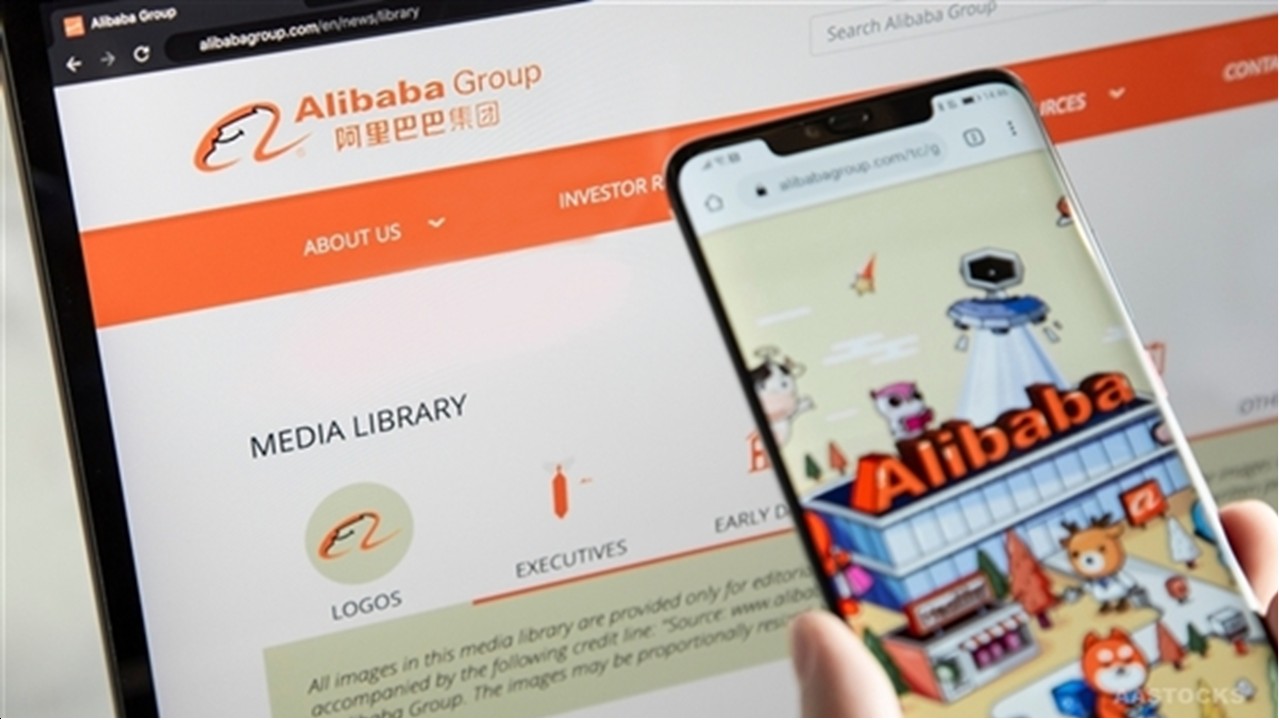
クラウドインテリジェンス事業が急成長
一方、最も成長率が高いのはクラウドインテリジェンス事業部門です。2025年3月期の売上高構成比は11%と、海外Eコマースに迫る規模となっています。純利益は全体の5%に過ぎませんが、前年比72%増えました。「アリババクラウド」ブランドでコンピューティングと人工知能(AI)関連サービスを手掛け、インフラやプラットフォーム、モデルをクラウドベースで提供しています。AIモデルのトレーニング・推論サービスも手掛けます。
アリババ集団は「AI+クラウド」を将来の成長エンジンと位置づけ、自社開発のAI基盤モデル「通義千問(Qwen)」シリーズやデータセンター、分散コンピューティング技術を基盤に収益を拡大しています。実際、クラウド事業は2025年3月期に2桁成長を達成し、AI関連製品の収益は2025年1-3月期まで7四半期連続で前年同期と比べ100%超の成長を記録しています。
ほかにも、アリババ集団はインターネット関連分野の企業を傘下に抱えています。主な子会社・出資先だけでも物流事業の「菜鳥智慧物流網絡」、フードデリバリーの「餓了麼(ウーラマ)」、オンライン地図の「高徳地図(Amap)」、動画プラットフォームの「優酷」、オンライン会議システムの「釘釘(DingTalk)」、生鮮スーパーの「盒馬鮮生(Freshippo)」などがあります。さらに、医薬品ネット通販の阿里健康(00241)、映画製作などのエンターテインメント事業の大麦娯楽(01060)(前社名はアリババ・ピクチャーズ)の2社が香港市場メインボードに上場しています。

「アリペイ」に潜むリスク、中国の金融行政と外資規制が影響
日本でよく見かけるアリババ関連のブランドと言えば、「アリペイ(支付宝)」かと思います。中国のスマホ決済サービスとしてテンセントの「ウィーチャットペイ(微信支付)」と市場をほぼ二分する高いシェアを誇り、海外に観光や出張に出かける中国人旅行者にとって必携のアプリとなっています。しかし、前段でリストアップしたブランドには「アリペイ(支付宝)」を含めませんでした。これには理由があります。
実は、アリペイを運用するアントグループはアリババ集団が33%を出資する企業ですが、現時点では連結対象ではありません。しかし、アリババ集団は、主力業務のEコマース業務で発生する支払いやエスクロー(代金預託)の処理をアリペイに依存しており、2024年3月期の財務報告書ではアントグループへの業務依存を事業・産業関連リスクの一つに挙げています。こうなっている背景には金融行政や基幹産業に対する外資規制、企業ガバナンスなどでに関する中国ならではの事情が絡んでいます。次回のコラムで詳しくご紹介します。




 人気ランキング
人気ランキング









 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



