2025年4月以降、東京株式市場では調整色が強まる場面もありましたが、7月には日経平均株価が4万円を固めるような動きになりました。この3ヵ月間の海外投資家と個人投資家の売買動向には、対照的な傾向が表れました。
海外投資家が17週連続で買い越し、一方で個人投資家は……
2025年度のスタートとなる4月初旬、東京株式市場では日経平均株価が急落。3月28日(金)の日経平均株価の終値は37,120.33円でしたが、週明けの3月31日(月)は終値35,617.56円と、1営業日で1,502.77円の下落(▲4.05%)となりました。その後も株価は下げ続け、4月7日(月)には30,792.74円の安値をつけました。
この下落の背景は、米国の関税政策への不透明感、景気停滞とインフレが同時に進行する懸念、そしてAI関連銘柄の調整という“トリプルショック”があったとされています。
こうした環境でも、海外投資家と事業法人は4月第1週目から毎週、現物株の買い越しを続け、なんと7月第4週目までの17週間、連続買い越し継続中です。しかしその一方で、個人投資家はこの17週のうち15週で売り越しとなり、動きは海外勢とは真逆でした【グラフ1】。
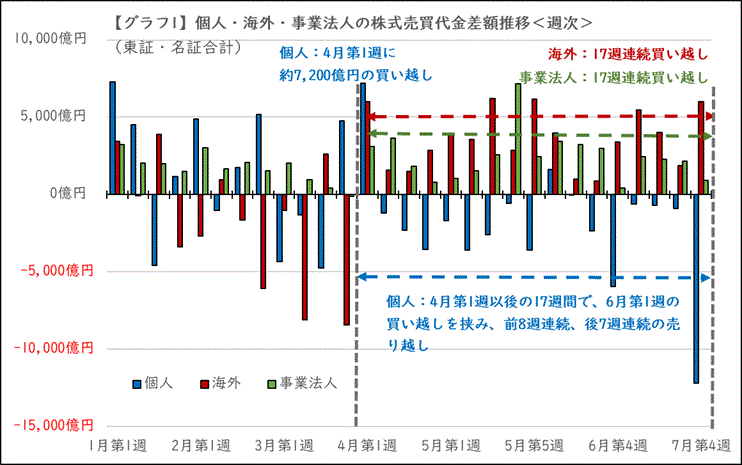
「投資部門別売買状況」とは?
【グラフ1】は日本取引所グループが公表している「投資部門別売買状況」に基づいています。投資家を事業法人、金融機関、個人、海外投資家などの主体別に分け、1週間にそれぞれが売買した株数や金額を集計したものです。東京証券取引所から、原則として毎週木曜日の取引終了後に公表されています。
集計は個別銘柄ではなく市場全体で、東証(プライム、スタンダード、グロース)と、名古屋証券取引所、およびこれらを合計した「二市場」の売買分が公表されます。資本金が30億円以上の証券会社経由の取引が集計対象です。
「投資部門別売買状況」では、市場に参加する投資家別に分け、それぞれの各部門の「買い」と「売り」、さらに「買い」から「売り」を差し引いた「差し引き」について、「金額」と「株数」を集計します。「差し引き」は、買い注文が多ければ「買い越し」で値はプラスになり、その逆は「売り越し」として値がマイナスになります。
買い越しをしている投資家は、その期間に強気だったといえます。つまり、4月以降の不透明感が漂う東京株式市場でも、海外投資家はずっと強気だったということです。円安によって日本株が割安だったのも一因でしょう。
株式市場は、株式のオークション会場ですから、「買いたい」投資家(需要)と、「売りたい」投資家(供給)の望む株価が一致した瞬間に取引が成立します。その瞬間の株価が「現在値」です。
「投資部門別売買状況」によって市場で誰がどのように動いたかがわかり、投資家心理の一端が見えるため、投資判断の際に参考にされています。
個人投資家は真逆の動き
一方、個人投資家は、4月第1週に約7,200億円もの巨額な買い越しを記録しましたが、翌週以降は8週連続で売り越しました。その後、6月第1週に買い越しに転じたものの、再び翌週から7週連続の売り越しに。特に7月第4週には1兆2,190億円の売り越しと、金額が急拡大しています。
当初は「株価が安くなったから買い時だ」と動いた個人投資家ですが、相場の急落が続く中でしだいに不安感を強め、売りを急いだのかもしれません。
7月下旬には日米間の関税交渉が妥結して相場が持ち直しましたが、不安感がぬぐえないのか「戻り待ち売り」が多く、「この先もどうなるかわからない」と考える個人の「利益確定売り」も重なって売り越し額が一気に拡大したと考えられます。
事業法人も17週連続買い越し=自社株買いの動き
冒頭の【グラフ1】では、海外投資家と個人投資家の売買は反対方向に動いているように見えますが、その陰で、事業法人も17週連続で買い越しを続けています。この買い越しの大半は「自社株買い」と見られています。
さらに【グラフ2】をみると事業法人の買い越しは長期的な傾向で、特に近年は巨額な買い越しとなっています。
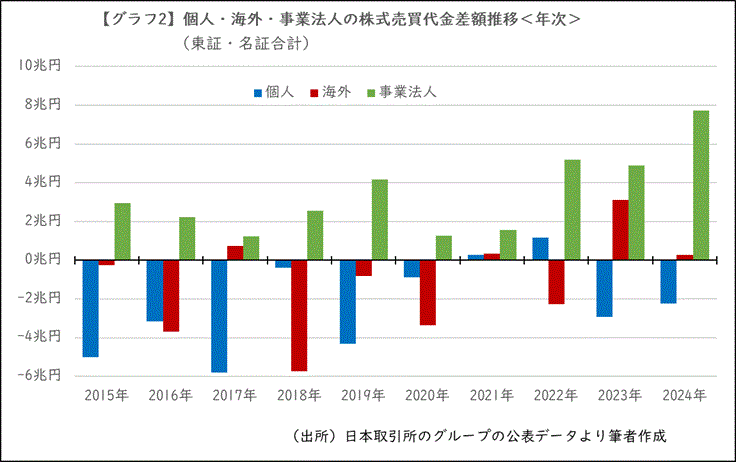
この背景には、東証のガバナンス改革(資本効率の改善)を受けて、上場企業が自社株を積極的に購入している流れが考えられます。持ち合い株式の売りを進めつつも、自社株買いを通じて株主還元を強化しています。こうした企業努力の積み重ねが、海外投資家からの評価にもつながっている可能性があります。
投資主体別売買状況を投資判断に活かす
このように、「投資部門別売買状況」からは、市場でどの投資家が強気でどの投資家が慎重かという投資姿勢を読み取ることができます。目先の株価やニュースに振り回されがちな局面でも、投資家ごとの動向を俯瞰することは、有用なヒントになるでしょう。
特に、個人投資家の動きが海外投資家と逆になる傾向があることを踏まえると、相場の潮目を感じ取る参考情報として活用できます。日本取引所グループが毎週公表している「投資部門別売買状況」は、無料で誰でも確認できます。マーケットの流れを俯瞰するヒントとして、定期的にチェックしてみてはいかがでしょうか。
【関連コラム】『投資ビギナーのための「投資部門別売買状況」入門』
【参考】『投資部門別売買状況』(日本取引所グループ)




 人気ランキング
人気ランキング












 連載
連載










 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



