米プリンストン大学のブルネルマイアー教授は、「金利を下げ過ぎると、預貸金利鞘の縮小を通じて銀行部門の自己資本制約がタイト化し、金融仲介機能が阻害されるため、かえって金融緩和の効果が反転(リバース)する可能性がある」と主張しました。「リバーサル・レート」は、時間の経過により徐々に切り上がり、量的緩和を行っている国は銀行の収益が悪化するため高めになる、と論じられています。
すなわち、金融緩和期間が長期化して、「リバーサル・レート」が、金利水準を上回ると、緩和効果がなくなるため、新たな対応策が求められることになります。
イングランド銀行(BOE)と米連邦準備理事会(FRB)は、第2次世界大戦中・後の戦時体制の時に、中長期国債を購入して国債の金利を抑制しましたが、その後はこの「パンドラの箱」を開けようとはしませんでした。おそらく、「パンドラの箱」の中の「リバーサル・レート」に気づいていたのかもしれません。
2017年11月13日、黒田第31代日銀総裁が、スイス・チューリッヒ大学での講演で「リバーサル・レート」に言及しました。黒田日銀総裁は、リバーサル・レートの提唱者である米プリンストン大学のブルネルマイアー教授の論文を引用して、金融緩和の効果が反転(リバース)する可能性があるという考え方を説明しました。
黒田日銀総裁は、2016年9月21日の「総括的な検証」において、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」(イールドカーブ・コントロール(YCC))を導入して、長期金利の低下を阻止するために、「下限」を設定しました。この「下限」は、金融機関の収益に悪影響を与え、金融仲介機能に悪影響を及ぼすことを防ぐ狙いがありました。すなわち、黒田日銀総裁は、「イールドカーブ・コントロール」の下限で、「リバーサル・レート」の考え方を導入していました。
その後、世界的にインフレが高進して、中長期債の利回りが上昇したことで、2022年12月20日の日銀金融政策決定会合では、イールドカーブ・コントロール(YCC)許容変動幅の±0.25%から±0.50%への拡大では、「上限」である+0.50%が注目されました。
YCC導入当時は、「下限」が重要視されていました。
2023年2月27日、植田次期日銀総裁候補は、参議院での所信聴取で、「当面はイールドカーブ・コントロール政策のもと、短期と長期の金利を現在の水準に誘導しつつ、必要に応じて国債を買う政策を続ける」と明言しました。金融緩和で金利が大幅に低下してある水準を下回ると、かえって副作用が大きくなり金融仲介機能が阻害される「リバーサルレート」理論については、現在、金融機関の自己資本は充実し信用コストも大幅に低下しているとして「金融仲介機能が阻害されているとは思えない。リバーサルレートにはまだ達していない」と述べています。
当分は、YCCの許容変動幅の拡大(±0.5%から±0.75%)、そして撤廃のタイミングが、日本国債10年物利回り、ドル円相場に影響を及ぼすことになります。




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング
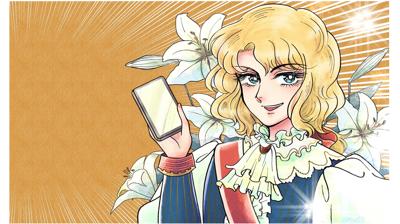



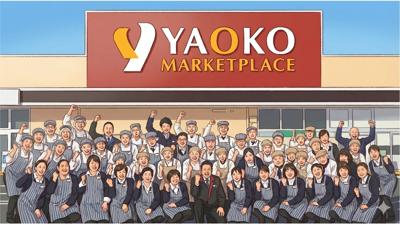















 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



