中国株を始めるためのキーワード。今回は中国で「小売業の奇跡」と称賛されている胖東来商貿集団(胖東来)について紹介します。
胖東来は河南省許昌市を中心に、スーパーマーケット、ショッピングモールを展開しています。中国で従来型の小売業の経営不振が目立つなか、胖東来は独自の経営モデルで業績を伸ばしており、2024年からは自社より遥かに規模が大きい業界大手の経営立て直しに乗り出しています。

胖東来と創業者の于東来氏
許昌は河南省中部にある地方都市。三国志で有名な曹操が後漢王朝の朝廷をこの街に移したことから、三国志ファンがよく訪れる場所の1つです。ただ、いまは胖東来も観光客が許昌を訪れるもう1つの理由にもなっているようです。
胖東来の前身は、同社現任会長の于東来氏が1995年に同市に開設した面積40平米の酒・たばこ販売店でした。1999年に許昌市で初の総合量販店を開き、2000年代は「胖東来」ブランドのスーパーマーケットやアパレルショップ、ショッピングモールが許昌市に相次ぎ開業し、同省の新郷市にも進出。それでも許昌市拠点の一地方企業に過ぎませんでしたが、22年ごろからその名は次第に全国に広がりました。于東来氏が情報サイト「聯商網」と手を組み、地方小売企業の経営者を育成するビジネススクールを立ち上げたのがきっかけだったようです。講師を務める于東来氏はネットでの露出度が増え、さらに「微博(ウェイボー)」や「抖音(TikTok)」などSNSで人気が急上昇しました。
「カリスマ経営者」である于東来氏の胖東来を見学に、多くの観光客や企業の研修団が許昌を訪れています。許昌市政府が公開したデータによりますと、24年のメーデー連休に同市を訪問した観光客が延べ480万人と過去最高を記録。胖東来が同市で展開するショッピングモール「天使城」、「時代広場」、「生活広場」の1日当たりの来店者数は延べ31万人に上り、市内にある「曹魏古城」など3カ所の三国志がテーマの名所の観光客数の合計を上回りました。ちなみに許昌市の常住人口は438万3000人(24年末時点)です。
于東来氏は25年1月、自身のSNSを通じ、胖東来の24年の売上高が約170億元となり、23年の107億元から約6割増加したことを明らかにしました。8億元超の利益を計上。従業員の平均月収は9000元を超えました。中国の国家統計局が発表した24年の全国の平均可処分所得が4万1314元、月間にして3500元弱となっていますから、地方都市にありながらも胖東来の賃金水準の高さが分かります。

経営不振の業界大手が店舗リニューアル、細部まで「胖東来要素」を取り入れ
永輝超市(601933)は胖東来の支援を受けている業界大手の1社。永輝超市は24年6月末時点で中国本土29省・直轄市にスーパーマーケットチェーンを943店展開する上場企業ですが、21年以降は赤字が続いています。業績不振からの脱却を図り、24年半ばから「独自の優位性を有する胖東来に学びたい」として、胖東来の支援を受けながら各地の店舗の改修に着手。25年1月までに十数都市で計36店舗をリニューアルしました。
直近では、上海市郊外の大規模ショッピングモール「金山万達広場」に入居する「金山万達店」が25年1月にリニューアルオープン。胖東来の経営手法を導入した店舗としては上海市で初めてであり、メディアの注目を集めました。
金山万達店は、細部まで「胖東来要素」を取り入れています。店舗入口には顧客休憩スペースを設け、そこで電子レンジや、ウォーターサーバー、スマートフォン充電器、身長体重計、血圧計、視力検査機などを無料で利用できます。授乳室やペット預かり所も設置。店内の商品陳列棚は高さをこれまでの2-2.4メートルから1.6メートルに変更。量り売りの食品は500グラム当たりの分量の目安を表記。胖東来で人気の高い惣菜や、ベーカリー、生鮮食品の売り場面積を大幅に増やしました。一方、価格を表示するPOP広告は、これまで使っていたA4用紙やさらに大きいポスター用紙から、小さなA6用紙に変更。永輝超市の副総裁で、全国の店舗リニューアルを担当する王守誠氏は、「以前は価格で勝負していたが、今は商品そのものの魅力で顧客を惹きつける」と変更の理由を説明しました。
販売商品も大幅に調整。これまでは1万3358種類の商品を取り扱っていましたが、うちの9418種類を取りやめた一方、6753種類を新規追加。調整後の商品構成は約8割が胖東来と同様。輸入品の割合を20%に増やしたほか、胖東来のプライベートブランド商品を販売するエリアを設けました。
また、胖東来を見習い、従業員の待遇を大幅に改善。賃金を平均で30%引き上げ、年間10日間の有給休暇を導入しました。従業員数も増やしました。従業員が仕事と生活をより良く両立できるよう、1日当たりの勤務時間を8時間以内に抑えるとしています。
胖東来効果で売り上げ10倍超も、大都市で新たな試練?
胖東来モデルはひとまず効果を上げているようです。永輝超市が胖東来の支援で改修した初の店舗、河南省鄭州市の「信万広場店」はリニューアルオープン初日の24年6月19日に188万元を売り上げました。改修前の1日当たり平均売上高の13.9倍に相当します。来店者数は6.3倍の1万2926人に達しました。永輝超市と同様に胖東来の支援を受けているST歩歩高商業連鎖(002251)が24年5月1日にリニューアルオープンした湖南省長沙市の「梅渓湖店」は、5月15日までの1日当たり売上高が10倍超の151万元、来店者数は7倍超の2000人に上りました。
もっとも、胖東来モデルの快進撃がいつまで続くかは未知数であり、永輝超市の金山万達店が注目される理由でもあります。上海市は24年の小売売上高が1兆7900億元で全国首位。市場規模は巨大ですが、Costco(コストコ)、Sam's(サムズ)、ALDI(アルディ)など世界のトップ企業が集結しており、競争は極めて厳しい。そもそも、ネット通販の台頭が永輝超市など従来型小売企業の業績不振の背景にあります。中国の巨大IT企業、アリババ集団(09988)とテンセント(00700)は2010年代半ば以降、オンラインとオフラインを融合する「新型小売り」を掲げ、従来型の小売企業に相次ぎ資本参加しましたが、「新型小売り」もこのところ下火のもよう。24年12月にもアリババ集団は17年に非公開化した百貨店チェーンの銀泰商業、20年に傘下に収めたハイパーマーケット大手の高キン零售(06808)の売却を発表しました。多額な売却損を計上しながらも保有株をすべて手放すことにしました。
許昌市で「奇跡」を起こした胖東来モデルですが、大都市では新たな試練が待ち受けているのかもしれません。
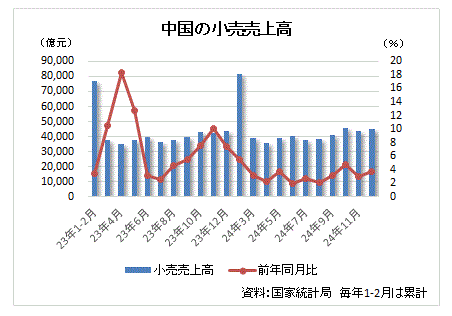




 この連載の一覧
この連載の一覧
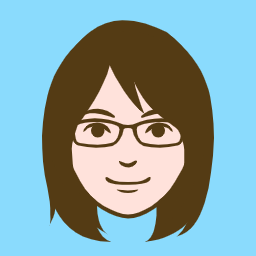
 人気ランキング
人気ランキング



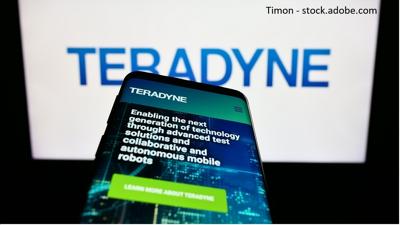


















 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



