中国株を始めるためのキーワード。今回は中国株の歴史に触れながら、「中国股民」について紹介します。中国語で「股民」は、一般的には個人株式投資家のことを指しています。
中国本土の株式市場、22年末時点の個人投資家比率は99.8%
証券振替決済機関である中国証券登記結算有限責任公司(CSDCC)の統計によると、2022年末時点で中国の株式投資家は2億1164万人に上っています。うち個人投資家は2億1163万人と、全体の99.8%を占めました。個人投資家の比率の高さが中国株式市場の大きな特徴です。

筆者が上海で暮らしていた2000年初頭頃、証券会社の営業ホールはまるでお年寄りの憩いの場でした。株価の表示されている電光掲示板の前に定年退職したおじいさん、おばあさんが集まり、世間話でもしながら相場を見守るのが日常の光景でした。もっとも、現在はスマートフォンの普及でネット取引が主流となり、いまはこのような営業ホールの光景はすっかり過去のものとなりました。

「株」に市民は冷ややか、深セン発展銀行も万科企業も公募は未達
この連載で以前にも触れましたように、中華人民共和国(新中国)の建国後、資本主義を象徴する株式と証券取引は、30年ほど姿を消しました。しかし、文化大革命が終わり、新しい時代を歩み始めた中国で、工場やビルの建設資金を集めたいという素朴な理由から「株券」が生まれ、発行市場の広がりが流通市場の誕生につながりました。1986年に遼寧省瀋陽市で店頭取引を行う「瀋陽証券取引市場」が開業。20世紀前半まで金融の都として繁栄していた上海市、改革開放の最先端を走る深セン市でも店頭市場が開設されました。
数十年にわたって資本主義を象徴する「悪魔」のような存在とされてきた「株」というものに対し、これまで投資とは無縁で生きてきた一般市民は、最初は冷ややかな目を向けていました。
1986年に国営企業の株式化が始まり、深セン市政府は農村向け金融機関6社をベースに、株式会社の深セン発展銀行股フン有限公司を設立することを決定しました。資本調達のため、1987年5月10日から一般向けに新株の公募を開始。額面20元の株券を79万5000株発行し、1590万元を調達する計画でした。ただ、市民の反応は冷淡で、募集が難航。市の幹部が率先して新株を購入し、国営企業数社も動員されて株式を大量に取得しましたが、最終的な発行株数は39万6500株、調達資金は793万元と、当初計画の49.9%にとどまりました。1988年4月7日に深セン発展銀行が深セン経済特区証券公司の店頭取引市場に上場したものの、年間の売買代金はわずか約400万元で、株価もずっと公開価格の20元付近で推移しました。
後に中国の不動産開発最大手に成長した深セン万科企業股フン有限公司も1988年に新株の公募を行いましたが、同じく未達に終わりました。
冷淡から熱狂へ、「深センの株を買えば大金持ちになる!」
状況を一変させたのは、深セン発展銀行の高配当でした。1989年に発表した1988年12月本決算の配当案は額面20元の1株につき7元の現金配当に加え、2株につき1株の株式配当という内容。銀行預金をはるかに上回る投資利回りが人々を驚愕させました。市民は投資の魅力に目覚め、1989年の株式の売買代金は前年8倍の3253万元に増えました。深セン発展銀行が1990年3月10日に発表した1989年の配当はさらに投資ブームをさらに刺激。「額面10元の1株につき10元の現金配当と2株につき1株の株式配当」という内容で、1988年配当とあわせると2年間で投資の元金をほぼ回収できたほか、持ち株は2株から4株に増え、株価の上昇で相当な含み益も出ています。
「深センの株を買えば大金持ちになる!」との情報が全国に拡散し、各地から人々が一攫千金を夢見て、深センに集まりました。店頭取引市場の前は人で溢れ、1990年5-6月の売買代金は3億7700万元に膨らみ、同年3-4月の6倍超、1988年と1989年の2年間合計額の14倍にもなりました。
当時の深セン市の株式市場は「三家五股」の体制(「三家」は株券の店頭取引を行う3つの金融機関、「五股」は店頭取引される株券5銘柄)でしたが、殺到する投資家で需給バランスが大きく崩れ、株価は急騰。「深セン市档案館」の資料によると、5月25日-6月17日のわずか20日間で、株価上昇率は深セン発展銀行が100%、深セン金田実業が140%、深セン原野実業が210%、深セン万科企業が380%、蛇口安達運輸が380%に達した。店頭取引の「三家」では対応しきれず、深セン市のあちらこちらで闇市場が乱立し、各闇市場の価格差を利用した裁定取引が横行。金儲けに目をくらんだ人々は勤務時間中にも投資に夢中し、役場や会社で「職場放棄」も横行しました。

社会の大混乱を受けて、当初は幹部が率先して株を買っていた深セン市政府は対応に追われました。中央政府では、そもそも「資本主義の株式市場」に反対する勢力が勢いを増し、「ただちに市場を閉鎖すべき」との意見が噴出。株式投資に目覚めたばかりの新中国の投資家らを待ち受けていたのは、初めて経験する株価の暴落とその後の政府による市場介入でした。次の機会でそれについて紹介します。




 この連載の一覧
この連載の一覧
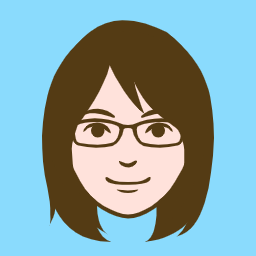
 人気ランキング
人気ランキング




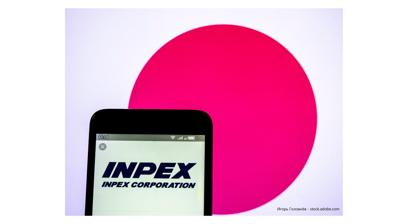
















 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



