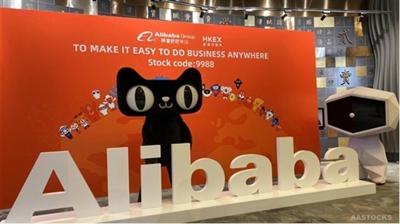テンセント、アリババ、百度、JDがサービス開始
中国と米国のインターネット企業が相次いで、同国の人工知能(AI)研究会社DeepSeek(ディープシーク)が開発した大規模言語モデルを利用できるサービスを始めました。
香港経済紙『信報』によると、中国インターネットサービス大手のテンセント(00700)のクラウド事業部門「テンセントクラウド(騰訊雲)」は、2日にDeepSeekモデルの提供を開始。3日にアリババ集団(09988)の「アリババクラウド(阿里雲)」と、百度(09888)の「百度AIクラウド(百度智能雲)」が続きました。JDドットコム(09618)のクラウド部門「JDクラウド(京東雲)」も4日に追随しました。
百度AIクラウドは「千帆プラットフォーム」 上で「DeepSeek-R1」と「DeepSeek-V3」の2モデルを提供し、超低価格プランや期間限定の無料サービスを展開しています。「ユーザーが安全かつ安定した環境でインテリジェントアプリケーションを構築できるよう支援する」とうたっています。
アリババクラウドも「PAIモデルギャラリー」からDeepSeek-V3およびDeepSeek-R1をワンクリックで利用できるようにしています。ユーザーはコーディング不要でトレーニングからアレンジ、推論までの全プロセスを実施できるので、モデル開発のハードルを大きく引き下げられるとしています。
米プラットフォームもDeepSeekモデルを提供
米国企業もクラウド上でAIを開発・利用できるサービスのメニューにDeepSeekモデルを加えています。『信報』によると、すでに米アマゾンのアマゾン・ウェブ・サービス(AWS)や米マイクロソフトの「Azure(アジュール)」、半導体大手の米エヌビディアがDeepSeek-R1を提供しています。
米国にしても、中国にしてもインターネット事業を手掛けるテック大手はそれぞれ自社開発の大規模言語モデルを構築してAI開発者に提供しています。低価格を武器に台頭したDeepSeekをサービスメニューに加えるのは一見すると「敵に塩を送る」行為に見えます。
しかし、AIサービスの利用料金が低下しても、AI活用が広がればクラウドやアプリの利用が増えますから、結局はインターネット・プラットフォーマー業務を手掛けるテック大手の収益拡大につながるという思惑があるようです。
前回ご紹介した通り、DeepSeek-R1は「オープンソース」で提供されており、誰でも利用できるのはもちろん、複製・改変・再配布が認められています。加えて、開発元の杭州深度求索人工智能基礎技術研究(英文社名はDeepSeek)は社名に示す通り、現時点では基礎研究に専念しています。テック大手にすれば、当面はAI事業の収益化で先行されないとみなされているのかもしれません。
米国はDeepSeekを容認したのか
もっとも、DeepSeekの今後が風満帆とは限りません。まず、半導体のように米国によって安全保障上の脅威とみなされる可能性があります。確かに、米テック大手の幹部によるDeepSeekへの評価はこれまでのところ表面的にはおおむね肯定的ですし、トランプ米大統領も1月27日、DeepSeekの登場について「たいへんポジティブな発展だ」と述べました。
しかし、DeepSeekが米オープンAIのデータを不正利用した疑いも浮上しています。ブルームバーグ通信は1月28日、オープンAIが提携先のマイクロソフトや米当局と連携して調査を進めていると報じました。
勢いづく中国のAIスタートアップ

月之暗面科技(Moonshot AI)のスマートフォン公式サイト
DeepSeekにとって、もう一つの潜在的な脅威は、ほかの中国AI企業との競争激化です。DeepSeekの台頭は一部の中国メディアとSNSユーザーから「米国によるAI支配を打破する快挙」ともてはやされたようですが、同時にAI開発を手掛ける国内のライバルを勢いづかせました。米国による半導体規制の下でも、工夫次第で世界的な競争力を持つAIモデルの構築は可能だとDeepSeekが実証した形になったからです。
例えば第40回でご紹介した月之暗面科技(Moonshot AI)は1月20日、大規模言語モデル「Kimi k1.5」を公開しました。DeepSeek-R1に遅れること数時間後という公開タイミングは、「負けていられない」という意気込みの表れでしょうか。DeepSeek-R1と同様に、性能指標は「OpenAI o1」と同程度だとしています。




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング




















 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事