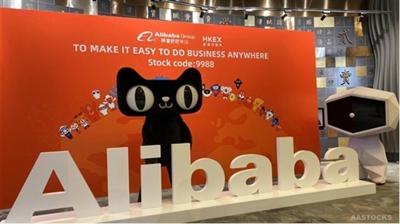上海総合指数と深セン成分指数が3連騰、国家隊の入場が支え
やはり、と言うべきでしょうか。関税を巡る米国と中国の対立がエスカレートするなか、中国の「国家隊」が株式相場の下支えに乗り出しました。連載第30回でご説明した通り、中国の証券市場では国家隊(ナショナルチーム)とは政府系の資金を意味します。国家隊の“主力選手”とされる中央匯金投資などが4月7日以降、相次いで中国本株の追加取得を表明すると、中国経済メディアには「国家隊が一斉に行動」(証券時報)などの見出しが躍り、市場が沸き立ちました。
トランプ米大統領が2日、中国からの輸入品に対する「相互関税」を34%にすると公表すると、中国政府は4日(同日は清明節の祝日で中国の株式市場は休場)、米国からの輸入品に同率の追加関税をかける報復措置を明らかにしました。これが嫌気され、週明け4月7日の中国本土市場では、代表的な株価指数である上海総合指数と深セン成分指数がそれぞれ前営業日比7.34%、9.66%下落しました。その後も米中間で関税上乗せの応酬が続きましたが、両指数はともに8日から3連騰しています。国家隊の入場が買い安心感を支えた材料になったようです。
中国人民銀行が買い増し資金を提供
国家隊による株式や上場投資信託(ETF)の買い増しは、その後の相場上昇を100%保証するものではありません。効果が長続きせずに終わった例もあることは、連載第30回でご紹介しました。ただ、今回は当局の株式相場てこ入れの本気度がこれまでになく高いと感じます。中国の財政部、中国人民銀行(中央銀行)、国務院国有資産監督管理委員会(国資委)がそろって支援を表明したからです。
人民銀の報道官は4月8日、24年10月に創設した株式買い増し・自社株買い専用の再貸付制度の資金を中央匯金投資に提供することで「資本市場の安定を断固として維持する」方針を明らかにしました。前日に中央匯金投資が発表した中国株式に連動するETFの買い増しへの明確な支援表明です。
中央匯金投資の責任者は7日、報道機関に対し、「我々は一貫して資本市場安定の重要な戦力であり、資本市場の“国家隊”だ。“平準基金”としての作用を発揮していく」と述べています。中央匯金投資の親会社である中国政府系ファンドの中国投資(CIC)は財政部が管轄していますから、中央匯金投資の公式サイトに掲載されたこの発言は財政部の考えを示したものといってよいでしょう。
同じく財政部の傘下機関である全国社会保障基金理事会も8日、「先ごろ国内株式の買い増しを行った」と発表し、今後も買い増しを継続する方針を明らかにしました。「常に長期投資、価値投資、責任投資の理念を堅持し、中国資本市場の発展見通しに強い確信を持ち、主体的に国家発展戦略に参画する」ことが主旨だとしています。
中国の国有企業、傘下上場企業の株式を追加取得
一方、国務院国有資産監督管理委員会は8日、直轄する国有企業(中央企業と呼ばれます)と、その支配下にある上場企業が持ち株の買い増しや自社株買いの規模を継続的に拡大するよう、全面的に支援すると表明しました。実際、中央企業の中国誠通控股集団、中国国新控股、中国電子科技集団(CETC)が7-8日に相次いで傘下上場企業の株式や技術イノベーション株、ETFを追加取得すると発表しています。
中国誠通控股集団と中国国新控股は、中国の国有資産を運営する「国有資本運営公司」と位置付けられていますから、株式買い増しは本来の業務の一つといってよいでしょう。しかし中国電子科技集団の主力事業は軍事用の電子機器や通信システムの開発です。同社が「積極的に資本市場における責務を果たす」として、傘下上場企業の株式を対象に20億元を超える買い増し・自社株買いを完了したと公表したことには、米国の政策への対抗措置の意味がありそうです。同社傘下で深セン市場に上場する監視システム大手、杭州海康威視数字技術(002415)は第一次トランプ政権時代の2019年に事実上の禁輸リストである「エンティティ-リスト」に収載され、2022年から米連邦通信委員会(FCC)によって米国内での販売を規制されています。

杭州海康威視数字技術(Hikvision )の監視カメラ
トランプ米大統領が中国に対して関税を武器にディール(取引)を迫る戦法をやめる兆しはいまのところありません。徹底抗戦している中国が自国の株式相場を浮揚させるには巨額の資金投入が必要になりますから、投資家が「株式買い増しをいつまで続けられるのか」という疑念を抱くのも当然です。しかし、国資委、人民銀、財政部という、中国の財政・金融を管轄する省庁が、実質的に株式相場下支えの“実弾“を提供すると一斉に宣言しました。これまでの中国株式相場の推移をみる限り、中国資本市場に対する信認を維持する効果があったようです。
財政部が保険会社も動員か
市場では、中国当局が中央匯金投資などの従来の「国家隊」とは別に、長期投資家を株式相場の下支えに動員するとの観測が浮上しています。中国通信社の財聯社によると、UBSは最新リポートで、2025年は中国当局の指導の下で長期投資家が継続的に安定した形でA株市場に投資する見通しを示しました。UBSの推定によると、中国本土の保険会社、ミューチュアル・ファンド、社会保障基金が中国株式市場に投入する資金の純額が、それぞれ1兆元、5900億元、1200億元に達する可能性があります。
実は、中国本土の主要な保険会社の一部は財政部の支配下にあり、「中央金融企業」と呼ばれています。具体的には香港・上海市場に重複上場する中国人民保険(01339/601319)、上海上場の中国再保険(01508)、中国人寿保険(02628/601628)の親会社である中国人寿保険(集団)公司、中国太平保険(00966)の親会社である中国太平保険集団有限責任公司です。UBSの予測が当たっていれば、こうした中央金融企業も中国企業の株式買い増しを表明することになるかもしれません。




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング







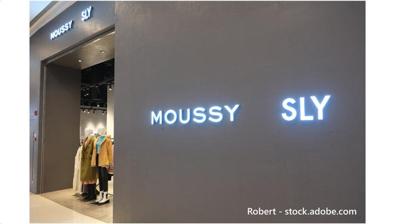













 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事