週明けの日経平均は一時31,000円を割り込む
週明けの日経平均は大幅続落。一時は31,000円を割り込む場面がありました。トランプ政権による関税に対する混乱が続く中、先週末の米国市場は主要指数が軒並み大幅安の展開。その流れを引き継いだ東京株式市場はパニック売りに近い状態となり、昨年8月急落後の安値(31,458円)を下回る展開となりました。
東証プライム市場の売買代金は概算で6兆9,800億円。値下がり銘柄数1628に対して、値上がりは6銘柄のみ。業種別では全業種が下落し、相対的に値を保った食料品、陸運、ゴム製品でも4%台の下落。非鉄金属、保険、証券・商品先物の3業種は10%を超える下落となりました。
個別では、今期の最終減益見通しを提示した安川電機(6506)がストップ安まで売られる場面があるなど急落しました。メガバンク3行や半導体関連が大幅に売り込まれ、ソフトバンクG(9984)、リクルートHD(6098)、日立(6501)などグロース系の主力銘柄も大幅安。防衛株や電線株も派手に下げ、古河電工(5801)やフジクラ(5803)はストップ安まで売られる場面がありました。
週足でみる日経平均の株価推移
図表は、日経平均株価の2023年8月頃からの週足のローソク足に加え、ボリンジャーバンド(20週)を掲載したものです。下位は、売られ過ぎや買われ過ぎなどをみるオシレータ系指標で代表的な相対力指数のRSI(9週ベース)の推移です。

ボリンジャーバンドとは、単純移動平均線を中心に標準偏差(σ、シグマ)を加えて描いたものです。標準偏差をボラティリティと考えます。一般的には標準偏差(シグマ)と標準偏差を2倍にしたもの(2シグマ)を単純移動平均線(中央値)からそれぞれプラスとマイナスの方向に広げ、合計5本のラインで構成されます。図表は、標準偏差を3倍にしたもの(3シグマ)までを反映した合計7本のラインで掲載しています。
価格が移動平均線の周りに正規分布していると仮定し、中央値に近い値ほど出現確率が高く、価格推移は-1シグマ~+1シグマに68.27%、-2シグマ~+2シグマに95.45%に収まるという考え方です。-3シグマ~+3シグマでは99.73%まで広がりますが、中央値から2シグマ以上乖離した値の出現確率は極めて低いといわれます。
コロナショックの2020年3月の急落時には1週間だけ-3シグマを下回った局面がありましたが、その2週間後からリバウンド相場に入っていった経緯があります。また、図表内で確認できる、昨年8月安値時も週間のザラバベースでは下回る場面はありましたが、終値ベースではバンドレンジ内まで戻して終えたことがわかります。このように、-3シグマはわずかな確率であるため、価格推移も一時的になることが多いといえます。
今回の急落場面では、先週の時点において、終値ベースで-3シグマを下回りました。今週も週初(7日)からの大幅安で下回る動きが続いています。しかし、2020年3月の急落時のケースを参考にすれば、-3シグマを下回るのは先週のみで一巡する可能性が高いといえます。今週は終値ベースではバンドレンジ内に収まることが予想され、まもなくの反転上昇も想定できそうです。
RSI(9週ベース)も売られ過ぎの水準まで低下しています。ボトムアウトには少し時間が必要かもしれませんが、昨年8月急落時の安値(31,156円)や2023年10月安値(30,487円)水準などが概ね支持線となることもあるでしょう。
一方、年初からの下落幅が大きくなったため、ボリンジャーバンドの中心線となる20週線が下落基調に変化しています。短期的なリバウンドは期待できますが、20週線に上値を抑えられ、38,000円台を回復するには相当な時間を要すことが考えられます。




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング






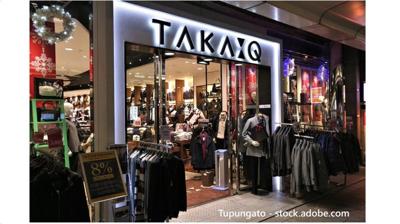













 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



