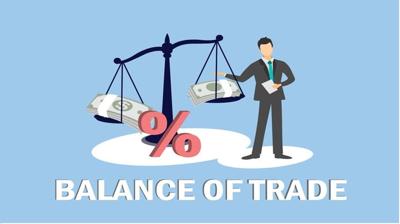ウォルマートの値上げ
ウォルマートはかつて西友を完全子会社化したことで、多くの日本人も名前は聞いたことがあることでしょう。
同社は米国での売り上げは断トツトップで、昨年1月末時点にはなりますが売上高は5280億ドル、2位のコストコが1840億ドルということで、比較するとその大きさが目立ちます。
店舗数もコストコの全米624に対して5200店舗以上となっています。
どれだけ巨大化ということが分かるかと思います。
そのウォルマートのレイニー最高財務責任者(CFO)は、5月中旬に消費者は早ければ今月下旬にも物価上昇を実感し始める可能性があると述べています。
これは、どういうことかと言いますと、中国をはじめとした輸入品の関税の影響で早ければ5月、確実に6月には店頭で価格が上昇する可能性があるということです。
小売りだけではなく、ナイキも値上げを始めています。
米中間はあまりにもばかげていたような高関税は両国が同意して115%引き下げることを決定しましたが、米国は基本的な関税10%を世界中に課しています。
更に、中国に対してはフェンタニル分の負担として20%上乗せして30%の関税が課されます。
レイニーCFOは同社が扱っているものは三分の二が米国産のものとしていますが、三分の一は海外産と述べています。
(細かく調べると、米国外依存度はより多いような気がしますが・・・。)
しかも、米国では新学期の6月と7月には買い物シーズンが本格化することになります。
よって、そのシーズンの値上げは、より大きな痛手が感じられるようになるでしょう。

5・6月の経済指標が更に難しくなるか
このことに関して、トランプ米大統領はソーシャルメディアで、「チェーン全体の価格引き上げの理由を関税のせいにするのをやめるべきだ・・・ウォルマートと中国は、よく言われるように『関税を甘受する』べきだ」と投稿しています。
確かに、ウォルマートの経営陣や創業者一族は米国の長者番付に多くの名前が記載されています。
また、多くのスポーツチームのオーナーがウォルマートの関係者だったりすることで、収益は巨大であるのは事実でしょう。
しかし、経営者という立場で、関税が上がり、輸入価格が上昇する中で、価格に転嫁しないことは不可能と思われます。
ウォルマートのような巨大チェーンがこのような状況であるのですから、より中小の米国輸入業者が一層関税引き上げで苦しむのは、誰が考えても分かり切ったことでした。
このような状況下にあることで、米連邦準備理事会(FRB)関係者が利下げに慎重な姿勢を見せるのは当然の結果です。
他国が利下げに動けるのは、米国の関税引き上げで輸出業者は苦境に陥るものの、自国の関税引き上げにならない場合はどちらがインフレに苦しむかは明らかでしょう。
レイニーCFOが言うように、本格的な価格上昇が5月後半から6月にかけてとなっています。
そして、一度始まった価格上昇は簡単に収まらない傾向にあります。
ロシアのウクライナ侵攻でオリーブオイルなどをはじめ価格が上昇しましたが、侵攻直後はさほど上昇率は大きくはありませんでした。
しかし、徐々に上がり、その値上げは年単位になり、上昇後はほぼ高値圏で維持されるのは、この数年の日本の状況をみてもわかることでしょう。
これから出てくる米国の経済指標は、値上げの影響がどの程度出てくるのかを見定めるのが非常に難しくなるでしょう。
おそらく夏あたりからは、インフレ指標や小売売上高などの指標に徐々に値上げが反映されてくることが予想されます。
今年の前半の指標で、米国のインフレ傾向や消費動向をつかむのは難しく、これから年単位でトランプ関税の影響が出てくることを覚悟しないといけないでしょう。




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング



















 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事