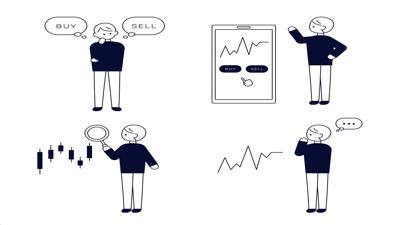今回解説していく通貨はトルコリラ円です。前回の解説(2月19日)からのトルコリラを巡る状況には大きな変化が見られました。3月中旬にはトルコ国内で政局不安が高まり、リラ円にも売り圧力がかかりました。これに対してトルコ銀行(中央銀行)は通貨防衛のために政策金利の引き上げで対応。中銀は昨年12月から利下げを開始し、金融緩和へと舵を切っていましたが、ここにきて急きょ政策転換を迫られる格好となりました。
政局・金融政策等で不透明感が高まっているトルコですが、チャート上でもトルコリラ円の状況を確認していきましょう。
トルコリラ円相場の週足分析 下落トレンド継続中
下図のチャートはトルコリラ円(try/jpy)の週足チャートになります。前回の解説(2月19日)からの推移を確認すると、2月後半には昨年9月16日につけたそれまでの過去最安値4.11円を下抜けて、3.56円まで大きく下値を広げることになりました。

現在は2023年8月高値を始点とする下降トレンドライン(チャート上の青色実線)に上値を抑えられる状況が続いており、以前よりも勢いは穏やかながら下落トレンドが継続中。
さらにチャート下部に追加した「DMI」で見ても、-DI>+DI(下落トレンド)を示唆しており、トレンドの強さを示すADXもはっきりとした上昇傾向にあります。
今回は「チャネルライン(チャート上の青色点線)」も加えてありますが、当面はこうしたツールなどを駆使しながら戻り売り方針で為替取引を行うのが無難でしょう。
トルコリラ円相場の日足分析 反発に至るには長い道のりが必要に
次に日足で直近の状況を確認してきましょう(下図のチャート)。チャート上の青色実線および青色点線は週足分析で紹介したものと同じものです。

今回は「一目均衡表」も追加してあります。現状は転換線と基準線はほぼ同値、遅行スパンと価格線も比較的近い水準にあり、明確に差が出ているのが価格線と抵抗帯(雲)の関係です。現在は価格線<抵抗帯となっており、今後は雲の下限が水準を切り下げていく見込み。同線を上回ることができるかが、リラ円相場の反発に向けた最初の関門となりそうです。
もっとも週足分析で示したように基本的には戻り売りが推奨される場面です。トレンド反転に至るには2023年8月高値を始点とする下降トレンドライン(チャート上の青色実線)を上抜けるだけではなく、昨年11-12月につけた直近高値のゾーン(チャート上の四角で囲った部分)を超えていく必要があるでしょう。
今後の取引材料・変動要因をチェック トルコ政局の不透明感がリラ相場の重し
最後に今後1カ月間の経済指標や重要イベントも確認しておきます。期間内には予定されていませんが、日銀は6月16-17日、トルコ中銀は6月19日に金融政策の公表が控えています。前述したようにトルコ中銀は直近の会合で急きょ金利引き締めに動いたほか、日銀も前回の金融政策決定会合で物価安定目標の実現時期を1年程度先送りするなど重要な決断を下しました。両中銀ともに次回の会合で再び金融政策方針を確認する必要があるでしょう。
一方で、トルコの政局不安についてですが、ここで改めて確認しておきます。3月19日にトルコ最大都市イスタンブールのイマムオール市長が拘束され、その後汚職で逮捕されるという事件が起きました。ただ、市長は容疑を全面的に否認。2028年に予定される大統領選挙では野党・共和人民党(CHP)の候補に指名されており、エルドアン大統領に対抗できる唯一の候補者と見られています。それだけに今回の逮捕は政治的動機によるものだとして、全国的に民主化要求デモが広がりました。
トルコの政治リスクが改めて意識された格好となっており、3月19日にはトルコリラ円が急落する場面も見られています。トルコの政局不安は今後もトルコリラ相場の重しとなる可能性がありそうです。
また、米国の関税政策にも引き続き注意が必要です。トルコリラだけでなく、外国為替証拠金取引(fx)市場全般が振らされる展開が続いており、12日には米中貿易協議で90日間の関税大幅引き下げが合意に至ったことが明らかになると、トルコリラ円も含めたクロス円がリスクオンの流れに沿って軒並み上昇する場面も見られました。
ただ、トランプ米大統領はこれまでも市場のムードをひっくり返す発言を度々してきた経緯があるため、市場がリスクオン方向へと傾いている現状でネガティブな発言が伝わった場合は相場への影響も相応に大きくなるはずです。個人的もこれ以上為替相場を荒らしてほしくはないですが、注意だけはしておかなくてはいけません。
その他のイベントは以下の通りとなります。
今後1カ月の重要イベント
5月23日 日本 4月全国消費者物価指数(CPI)
6月3日 トルコ 5月CPI




 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング







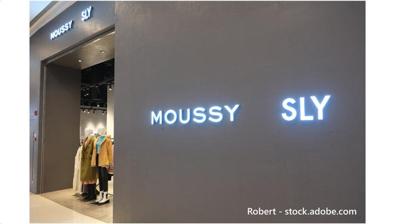













 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事