豪ドルは上値の重い動き
今年に入って、豪ドルは上値の重い動きが続いています。貿易で関係性が強い中国の景気の不透明感やトランプ米政権の通商政策が重しとなっています。また、対円では日銀による追加利上げ観測という金融政策を巡る方向性の違いが上値圧迫要因となっています。
豪ドル/ドルは昨年10月上旬に2023年2月以来の高値となる0.69ドル半ばまで上昇したが、そこから下げに転じ今年の2月には0.60ドル台後半まで下落しました。下げは一服するも0.64ドル近辺を戻り高値に上値の重い動きが続いています。トランプ米政権の関税による米景気懸念を背景にドル高が失速したことが下支えとなりましたが、先行きについてはドル高の再燃が警戒されます。
豪ドル/ドルの週足

豪景気は底打ちか
コロナ禍の影響が一巡した後、豪経済は住宅需要の高まりを追い風に不動産市況は急騰する事態に直面しました。豪準備銀行(RBA)は物価と為替、不動産市況の安定を目的に高金利政策を維持したものの、物価高と金利高の共存が長期化するなかで家計消費をはじめとする内需に下押し圧力が掛かる動きがみられました。よって、内・外需双方で実体経済に下押し圧力が掛かり、景気減速懸念が強まりました。
ただ、最近の実質賃金の伸びはプラスに転じるなど、家計部門を取り巻く環境は変化しています。また、昨年末にかけての中国景気は底打ちするとともに、トランプ米政権の発足を前に対米輸出に駆け込みの動きが出るなど、外需も押し上げられました。よって、昨年10-12月GDPは前期比年率+2.35%と2年ぶりのペースに加速しており、中期的な基調を示す前年同期比ベースも+1.3%に加速するなど底打ちの動きが確認されました。
豪インフレは一段と落ち着くか
インフレはRBAが定める目標域を大きく上回る推移をみせるとともに、2022年末には一時33年ぶりとなる高水準となったものの、商品高の一巡を受けてその後は頭打ちに転じる動きをみせてきました。
2月のインフレ率は前年比+2.4%に鈍化している上、コアインフレ率、RBAが重視する物価統計のいずれも目標域(2-3%)に収まるなど落ち着いた動きとなりました。商品高の一巡に加え、アルバニージー政権が実施した電力料金を対象とする補助金政策の効果も重なり、インフレはRBAが定める目標域で推移するなど落ち着いた動きとなりそうです。
RBA、5月会合で追加利下げも
RBAは2月会合で4年ぶりの利下げに踏み切り、政策金利を0.25%引き下げ4.10%にすることを決定しました。ただ、先行きの政策運営について慎重姿勢を崩さない考えを示すなど「タカ派」的な内容でありました。
ただ、足もとのインフレは落ち着いた動きをみせており、予算案に伴う物価への影響は限定的と見込まれるものの、RBAが月次以上に四半期ベースの物価統計を重視していることに鑑みれば、4月会合では様子見を図るも5月会合で追加利下げに動く可能性があります。
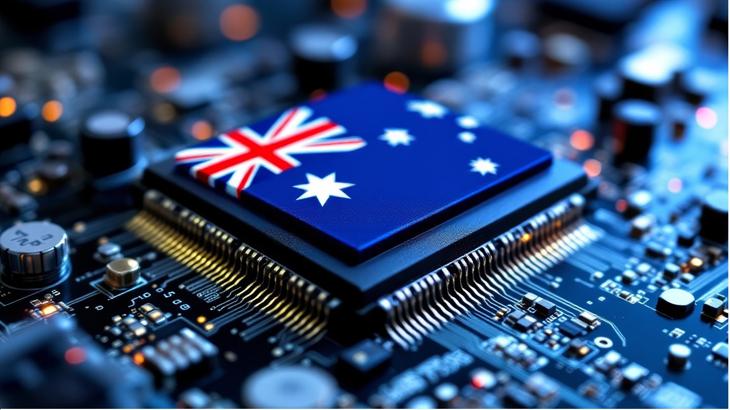



 この連載の一覧
この連載の一覧

 人気ランキング
人気ランキング





















 話題のタグ
話題のタグ
 関連記事
関連記事



